��� �d�g�L���̐��n��
1981�N�[1988�N(���a56�N�[���a63�N)�P�X�W�O�N��͏��a���ォ�畽������ւƈڂ�ς��Ŋ��̈ꎞ��ł��褓d�g�L���ƊE�͂P�X�W�X�N�����ɁA�����̉q��������������������V�������㑦����q�����N��ƌ����ɑ�������������}���鎖�ƂȂ�
�䂪��������ɔs�ꕽ�a���Ƃ�ڎw���đ����ݏo�����P�X�S�T�N���珺�a����̏I��(�P�X�W�X�N)���̂S�S�N�Ԃ̐�����o�ς��܂߂��䂪���̕��݂́A�N�����z�������Ȃ��������̕������琢�E�̐�i���ɒǂ����o�ϐ����𐋂�����ɐ��E�Ɋ�����o�ϑ卑�̒n�ʂ�s���̂��̂Ƃ����̂ł��顂P�X�W�O�N��͂P�X�V�R�N�̑�ꎟ�I�C���V���c�N�����ĂP�X�V�X�N�̑�I�C���V���c�N���o�Ă��̖����J����P�X�W�T�N�'�W�U�N�̉~���s�����������Ă��̌㏇���ȕ��݂��n�߂��̂ł���
�@
�P�X�V�O�N��̏I�Ֆu�������C�����v�����_�@�Ƃ�����I�C���V���c�N�ɂ��䂪���o�ς͂P�X�W�O�N�ȍ~'�W�R�N�܂Ōi�C�̌�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ���A���̌i�C��ދǖʂ��P�X�W�S�N�ɓ���A�o��ݔ������Ɏx�����g���ɓ]�����̂ł��顂������P�X�W�U�N�ɓ������{�o�ς͉~���ɂ��A�o�̒�ؤ�ݔ������̐L�єY�ݤ�l����̒���Ȃǂɂ��i�C�������̈�r��H��������̌i�����P�X�W�V�N��]���ē����̊g��ƌl����ɂ��g���ɖ߂�P�X�W�O�N��̏I�Ղł���P�X�W�W�N�̓��{�o�ς͋v���Ԃ�ɖ��邳�����߂��Y�ƊE�͋����čD�i�C�ɐ������ꂽ�̂ł���B�~���s���ɂ��ăG�R�m�~�X�g���X�v�Y���͂��̒�����킽���̐��o�ώj��̒��łP�X�W�V�N�㔼����̌i�C�̗v�������̗l�ɋL�q���Ă��顂���ɂ��ƂP�X�W�U�N�̂P�P�����s���̒�Ť���ꂩ��i�C����'�W�V�N�㔼����}���Ȍi�C�̏㏸���N���蕽���i�C���W�J������i�C�̍ő�̌����͂ͤ�~���f�t�����ɘa���邽�߂Ɏ��{���ꂽ�ϋɓI�Ȍ��������̊g��ƌ��łł��顂����Ċe��Ƃ��ߑ㉻�������s������ɂ���Đ��Y�������߉~���ɑΏ���������̂��Ƃ������̊g��Ɠ����̊g��ɑ傢�Ɋ�^�����Əq�ׂĂ��顏�������߂���̗v���͉~���ł��肱��ɂ���ď����������������ĉ~���s���͈ӊO�ɂ������i�C�Ƃ��������哱�^�̑�u�[���݂����A�P�X�W�U�N�P�P������P�X�X�P�N�S�����̂T�R�P���Ԃ̕����i�C���������̂ł��顈�����̂悤�Ȍo�ϊ����ɂ����čL����͂ǂ̂悤�Ȑ��ڂ�H���Ă����̂ł��낤����P�X�W�S�N�P�O���P�W�������s�ŊJ�Â��ꂽ��R�Q�����œ����̖����A����쏇��������A�̒��ŁA�P�X�W�O�N��̖����ƊE�͢�ᐬ�������lj����j���[���f�B�A��ƌ�����O�d��ɒ��ʂ��Ă���Əq�ׂ�ꂽ������ɂ��̌��t�ɏے������ƊE���̒��œd�g�L���������܂łƂ͈�����������ǖʂ��}�����̂ł��顈ꌾ�Ō����P�X�W�O�N��͢���l������̉c�Ɛ헪�̍\�z������߂��鎞��̒����ł���������̎���̌i�C�f���ăe���r�L����͂P�X�W�T�N�ɂ͖��ԕ��������ȗ��Œ�̐L�ї��ł���101.9%�����'�W�U�N��102.6%�ƑO�r�Ɉꖕ�̕s����`�������̂ł��顖�����W�I�L�����'�W�T�N103.8%�ƌ����������̂�'�W�U�N�ɂ�101.3%�ɗ������̂ł��顑����Ă��̎���̓e���r�L����哱�Ő��ڂ��Ă����ƌ����悤�B�L����̑S�̓I���ڂ͕ʓr�L�q���鎖�Ƃ��邪����̎���e���r�L����ɂ��Ă��N�X���̓��e�ɕω������܂�Ă���������e���r�̍L����̒��Ő�߂�X�|�b�g�L����̑���Ƥ��s�s�𒆐S�Ƃ���L����̏W�����X���������Ȏ��ۂƂ��Č���Ă�������̌X���͊��ɂP�O�V�O�N��I�Ղɂ��U�����ꂽ��������ɗ��đ傫�ȗ���ƂȂ��ē����n�߂��̂ł���
���̑傫�ȗv���͉��l�ς̑��l���ƌ�������I�ϊv�Ƥ����ɑΉ����频��i�폭�ʐ��Y�����i�T�C�N���̒Z�������L����̔̔������^���p�����L����̃}�[�P�b�e�C���O�����ɑ傫�ȕω������܂�Ă������Ƃɂ����̂ł��顂����}�[�P�b�e�C���O�֘A�ɂ��Ă͕ʍ��ŏq�ׂČ������
�}�@34�@�S���}�̕ʍL�����
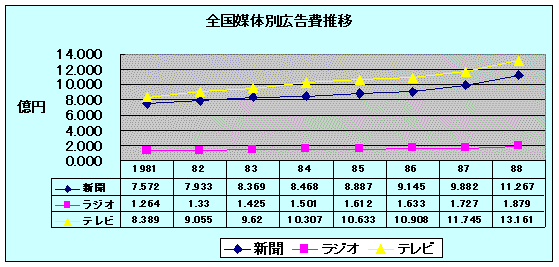 �@ �@��L�Ɍ���ʂ�P�X�W�T�N�'�W�U�N�͐V������W�I��e���r�e�}�̂Ƃ��ᐬ����]�V�Ȃ����ꂽ��P�X�W�V�N�ɓ���L����������̒����������A��'�W�W�N�ɂ͊e�}�̂Ƃ��啝�ȐL�ї��������鎖���o������P�X�W�T�N�ȍ~�̍L������Œ��ڂ��ׂ��ͤSP�L����ƃj���[���f�B�A�L����ł��額L����̃}�[�P�b�e�C���O��@��'�W�T�N�'�W�U�N�̕s�����_�@�Ƃ��Ĕ̔��ɒ��������Z�[���X�v�����[�V�����L���ɏd�_���u�����@�^�����܂�������������V�������f�B�A�ɑ���L����p���������肷��`�œ����n�߂���d�ʂ̓��{�̍L������P�X�W�V�N����܂ł̐���͈͂����肵�ĐV�����������̗p�����̂����̂悤�Ȏ��̂܂��Ă̎��ł��낤�����܂ŏq�ׂė����l��SP�L�����'�W�T�N�ȍ~�e�}�̂�ʂ��ăg�b�v�̍L����ƂȂ��Ă��顓���SP�L���̒��ł�DM���܍���L�����D���ɐ��ڂ��Ă�����̂͑S���I�X���ł��邪��k�C���n��ɉ����Ă����l�Ȍ��ۂ������鏈�ł��褍L�����f�B�A�Ƃ��ĕ���Ȃ����݂Ɛ�����顖���j���[���f�B�A�L�����P�[�u���e���r�̍L���o�e���唼�ł��邪����ɃP�[�u���e���r���܂߂��q���f�W�^�������������O�̎��{�Q���ɂ��傫�ȓ����������Ă��荡��̍L���ʂɂǂ̂悤�ȉe����^����̂��͗\���ł��Ȃ����[���S�������đΏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��}�̂ƂȂ��
�P�X�W�T�N�ȍ~�e���r�L����ɂ��V�����ω����\��n�߂���O���ł��G�ꂽ�������L����̃}�[�P�b�e�C���O��������e���r�L���̗��p�ʂő�s�s�W���ɂ��L����̌����I�^�p������Ă���܂ł̔ԑg��CM�I�o�����̔��ɒ��������X�|�b�g�L���ւ̃V�t�g�ւ̓]���������Ȏ��ۂƂ��ē����n�߂��̂ł���B
�@�}�@35�@�e���r�L����n��ʓ����z�V�F�A
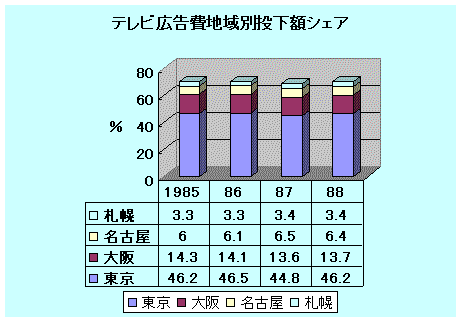 �@�P�X�W�T�N�ȍ~�̃e���r�L����̐��ڂ�����Ɗe�n��̃V�F�A�͖��N�قړ������x���Ő��ڂ��Ă��顂���̓^�C����X�|�b�g��������܂߂��O���X�L����ł��褑�s�s�W���̓����̓X�|�b�g�L���Ɍ����ł��邪�A���E��E���n��͂��Ƃ��S���e�n��ł��e���r�����̔�d�̓^�C���ɔ�ׂăX�|�b�g�ɃE�G�C�g��������X���ɂ���B�����ē���㥖��n��̃X�|�b�g�V�F�A���N�X�g�傷��̂ɑ������ȊO�̒n��ŃX�|�b�g�V�G�A�͔N�X�����̌X�������܂��Ă��顂��̌��ۂ��Ȃ�Ƃ��Ă��j�~��������L����̖ڂ�n���Ɍ��������鎖������̒n���ǂɂƂ��čő�̉ۑ�Ɛ����Ă����̂ł���
���Ɋe�n��X�|�b�g�V�G�A�̐��ڂ����鎖�Ƃ���
�@
�@ �}�@36 �@�S����v�n��X�|�b�g�����V�F�A
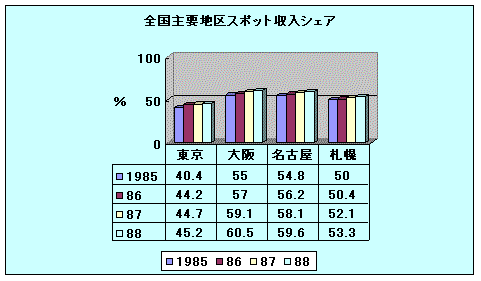 �@ �@��̃O���t�́A�S����v�s�s�ɂ�����^�C��(����������)�ƃX�|�b�g�����V�G�A�̐��ڂł��顂��̕\������X�|�b�g�����̗��ꂪ��s�s�𒆐S�Ƃ��ĉ������Ă�����̂������o���顓d�ʂ̒��������ɂ���Ă��S�����x���̃e���r�L������N�X�X�|�b�g�̃V�F�A�����債��P�X�W�W�N�ɂ�50%��W�X�N�ɂ�52.1%�ƃe���r�L����̃��C�����i�Ƃ��Ă̈ʒu���m�������邱�Ƃ�����Ă���B����̃O���t�}36������X�|�b�g�L����V�G�A�����㖼�𒆐S�ɏ㏸����N�X��s�s�W�����̌X�������܂褔��ʂ��̑��n��ւ̃X�|�b�g�����z�����̌X����ǂ݂Ƃ鎖���o���悤�
�@�}�@37�@�S����v�s�s�e���r�X�|�b�g�����z�V�F�A
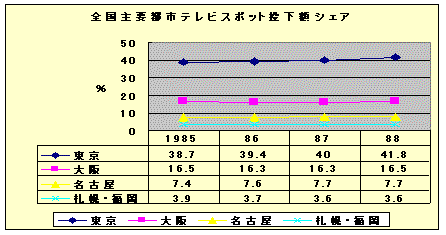 �@ �@1980�N��ɓ��褂���܂ł̍��x�������x���Ă������ʐ��Y�[��ʔ̔��[��ʏ��ƌ����S�����I�ȃ}�X�}�[�P�b�e�C���O�͏���҂̉��l�ς����l�����钆�ōL����̃}�[�P�b�e�C���O�����ɂ��傫�ȕω��𑣂����ʂƂȂ����
�����C�x���g��Z�[���X�v�����[�V�����̏d����G���A�}�[�P�b�e�C���O�̓W�J������Ĕ̔��ɒ��������L���v�悪�嗬�ƂȂ褍L����̌����I�ȓ����ړI���L����̑�s�s�W�����X���ɔ��Ԃ������鎖�ƂȂ���������ăe���r�̗��p�`�Ԃɂ������̏ɑΉ�����悤�ɑ傫�ȕω����n�܂����̂ł��顂���܂ł̃e���r�L���͔ԑg���嗬�ł��褃X�|�b�g�L���͏��i�̔̔��L�����y�[���ɘA������`�ŗ��p����W���X�|�b�g(����ꂽ���Ԃɑ�ʂ̍L�����d�_�I�ɘI�o����)�^�̐헪���i�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꤔԑgCM�͊�Ƃ̃X�e�C�^�X�����߂鎖���Ӑ}������ƍL���I���i����������������i�폭�ʐ��Y�[�̔��̂��߂ɂ͏��i�̔F�m�������ߔ̔��ɒ�������L���I�o�ɏd�_���u�����l�ɂȂ�X�|�b�g�L����^�C���L�����ǂ������ăe���r�L����̎嗬�ƂȂ��������@���̎��͑O���ł��q�ׂ��ʂ�ł���B
������̎���L���ƊE��킯�Ă��L����̑������l�b�g���[�N�ɂ��d�g�����Ƥ�i�V���i���L����̏o�e�Ɉˑ����Ă����e���r�ƊE(�n��������)�𒆐S�ɁA�G���A�}�[�P�b�e�C���O�̐��i�ɂ���ēd�g�L�������������悤�Ƃ��铮�����}���ɍ��܂������������L����̊Ԃł�����̔̔��������X�ɋ��߂Ă����ׂɂ́A�S�����I�ȃ}�[�P�b�e�C���O�ł͂Ȃ��e�G���A���̂��ߍׂ��ȑΉ����s���ł���Ƃ̍l�����L�܂��Ă����̂����̎�@����w����グ��͂ƂȂ����
�@
�e���r�L����̑�s�s�W���������݉�����k�C���n��}�[�P�b�g�ɑ��铊���L����V�F�A���N�X�������ޏɓ����e���r�W�҂̊�@���͍ō����ɒB����������Ă���܂ŏq�ׂĂ����悤�ɒn���̍L����̊�������}��ׂɂͤ�n�������ǂ��i��Ţ�G���A�}�[�P�b�e�C���O���ϋɓI�ɓW�J���ׂ��Ƃ̗L���҂̔�������ь�������w�i�ł��������
�P�X�W�T�N�P�O���k�C���n��e���r4�Ђ�HBC�STV�HTB�uhb(�������NTVh�J�nj�5��)�В���͂��̂悤�ȏ�Ŕj����ׂɂ̓e���r�e�Ђ��������ċ����L�����y�[����W�J���鎖���K�v�Ƃ̔F���ɒB����������Ɋe�Љc�ƊW�����𒆐S�ɍݎD�e���r4�ИA�����c��ݗ����ꂽ�
���̋��c��ł͗�'�W�U�N�P���Q�U���ݎD�S�Ђ̉c�ƒS�������ȉ��{�Х��������x�Њ������ꓯ�ɉ�ē��O�s��ɑ���PR�����̂������k�C���n��X�|�b�g�V�F�A�����߂�ׂ̋�̍����^���ȓ��c��W�J�����
�k�C���s��荞��ōs���ׂɂऒ����L���傪�k�C���n��̃e���r�ǂɂǂ̂悤�ȃ}�[�P�b�e�C���O���������҂��Ă���̂������̃X�e�[�V�����}�[�P�b�e�C���O�����ɑ���v�]�͉������e���r�W�҂��������������邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ̊ϓ_���礒����L����̃}�[�P�b�e�C���O�S���������`�S�������̕��X�ɂ��u�������肢���鎖����L�����y�[���������X�^�[�g������e�u�t�Ƃ��ٌ������ɒn�������Ɋ��҂���̂͒n��̏��Z���^�[�Ƃ��Ă̋@�\�ł��褒n��̐��������̏�M�@�\�ł���Ɨ͐����ꂽ������̎����܂��Ă��̌�e�e���r�ǂƂ��n����ԑg�ɐ��͓I�Ɏ��g�ގ��ƂȂ�̂ł��顂��̃L�����y�[���͊e�Ђ�������芲���ЂƂȂ蓌���s��ɑ��Ă�PR���̔��s����s��Ɍ����Ă͓����̖k�C���m�����H�F�O�����n�߂Ƃ��铹���G�R�m�~�X�g��W���[�i���X�g���̍u�����p���I�Ɏ��{����������Ɗԥ�n��ԋ������������钆�Ńe���r�e�Ђ����Q���ăe���r���f�B�A�̊������Ɏ��g�p���͍����]�������ׂ��ł��낤�
�@
���̖ړI�ɉ����ēW�J���ꂽ��̓I����Ƃ��āA�����S�ǂ��Q�����čs��ꂽ�̂��m�����[���k�C���L�����y�C���n�ł������B�P�X�W�S�N�T�b�|���E�r�[���T�C�h����A�k�C���������̈������L�L�����y�B�������^�������Ƃ̐\���o���A�ݎD�}�X�R�~�e�Ђ����Â��Ď��{���邱�ƂƂȂ�A�P�X�W�U�N�W���R�O���ߌ�P������T�S���ԁA�ŏ��̃C�x���g�Ƃ��ām�r�A�g�[�N�E�C���E�T�c�|���n���e���r�S�Ђ̋�������A�����ԕ��������{���ꂽ�B���̊��͑S���I�ɂ��傫�Ȕ������ĂсA���N�X���S�����s�̏T���V���ɂ́m�T�b�|���r�[�����d�g�W���c�N�H�n�Ƃ����^�C�g���Ŏ��̗l�ɏЉ�ꂽ�B
�m�W���R�O���ɖk�C���n��ŕ�������鐳���P���Ԃ̃g�[�N�ԑg�́A�Ȃ�ƁA�n���̖����e���r�ǂ����z���M�A���ׂē����ɕ�������ƌ�������������B���Ƃ���̃u���b�N�̎��Ƃ͌����A�S��������В̓����ԑg�𗬂����͗ޗႪ�Ȃ��B�T�b�|���E�r�[���ł͖k�C���̈ꑺ��i�^�����e�[�}�[�ɂ������������������̂�������������A�ƌ���Ă���n�B
���̌ケ�̊��̓��W�I�E�e���r�T�C�}�����Ƃ��ČܔN�]�p�����đ�����ꂽ���A�k�C���n��Ƃ����n���G���A����s�s�W���̍L���헪�ɑ傫�Ȋ�@���������A�n������f�B�A���A�g���Ď��g�G���A�}�[�P�b�e�C���O�̋�̓I����ƌ����悤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�P�X�W�O�N��͕������f�B�A�̕���ł��m�n��ɍ����������������n�����߂��鎞��ł���A�n���̎����ƌ����傫�Ȑ����ڕW�Ɍĉ����Ēn��Љ���傽��^�[�Q�b�g�Ƃ������ԑg���W�J����鎞��I�����ɂ������B����L����̓d�g�L�����p������܂ł̔�����厲�Ƃ����}�[�P�b�e�C���O�c�[���Ƃ��Ẵ��W�I�E�e���r�̂b�l���王���҂̃j�[�Y�ɉ������ɑ傫��������ς�����A���̂��Ƃ��n����ԑg�̂b�l�Ƃ����`�œW�J����A�ԑg�Ƃb�l�̗��ʂ̊������ɔ��Ԃ������鎖�ƂȂ��B�@
�n����ԑg�̐�ڂ������̂͂g�a�b�e���r���ߌ�U����ɕҐ��������[�J�����C�h�j���[�X�m�e���|�[�g�U�n�ł����B�����͊J�n�͂P�X�V�T�N�Q���R���ł��邪�A�����ߌ�U����ƌ����Ύq���Ώۂ̎��ԑтƂ��āA����Ȃǎq���Ώۂ̔ԑg��ം߂��Ă������ԑтł������B���̎��ԑт��q���̎��Ԃ���j���[�X�Ƃ����ԑg�ɕς���ƌ������Ƃ͉c�ƃT�C�h���猩��ɂ߂đ傫�Ȗ`���ł���A���肵�Ă�����������������鎖���뜜�������͌����܂ł������B���������̔ԑg�Ґ��͎���̗���ł���A�j���[�X�ԑg�̉c�Ɖ��͍���Ƃ�������܂ł̃C���[�W�@���āA�����J�n�����ǂ��Ď������̋}���Ƌ��ɂb�l�X�|���T�[�̎��v�������A����ꂽ�����g������c�ƕ���̊������ߖ��������B���̔ԑg�͍����܂ő����Ă��邪�A�Q�O�O�O�N�P���P������͑������V���Ɂm�e���|�[�g�Q�O�O�O�n�Ƃ��čăX�^�[�g�����B
���̂悤�ɒn����ԑg�͐悸���[�J���j���[�X�𒆐S�ɓW�J���ꂳ�ꂽ���A�g�a�b�e���r����ڂƂȂ��Ă��̌�P�X�V�X�N�R���ɂ͂r�s�u�e���r�m�Y�[���C���I�I���I�n���X�^�[�g���A�������_�@�Ƃ��Ċe�ǂƂ����A�[�̎��ԑтł̃j���[�X�ԑg�ł̋��������������B�n����ԑg�̓j���[�X�ԑg�ɂ�������l�ɓd�g�L���̑Ώ۔ԑg�Ƃ��Ă����S�ɒ蒅���A�W���[�i���Y���ƃR�}�V�����Y����������ʂ������炷�ɂȂ����B���̂��Ƃ��g�a�b�e���r�́m�ق��ƂȂ��ƂQ�Q�n�r�s�u�e���r�́m�ǂ����C�h�P�Q�O�n���ւƔ��W����B�g�a�b�e���r�́m�ق��ƂȂ��ƂQ�Q�n�͖{�i�I�Ȓn����ԑg�Ƃ��ĂP�X�W�U�N�P�O���V���i�j�ߌ�P�O������T�S���̔ԑg�Ƃ��ăX�^�[�g�������A��'�W�V�N�P�O���U������̓^�C�g�����m�ق��ƂȂ��Ƃg�n�j�j�`�h�c�n�n�Ƃ��Čߌ�W������T�S���̔ԑg�ƂȂ�B���̂悤�ɒn���e���r�ǂ��v���C���^�C�����g���Ď��Дԑg�𐧍삷�邱�Ƃ͉���I�ȏo�����ł���A�n���̎����\�����邱�ꂩ��̃��f�B�A�̂�������������������������B����ɑ��r�s�u�e���r�ł��J�Ljȗ����߂Ẵv���C���g�ł̐��삪�s���鎖�ƂȂ������P�X�W�X�N�P�O���P�����i���j�ߌ�P�O���R�O������n�܂����m������Y�̃X�[�p�[�T���f�[�n�ł���B�k�C���G���A�łg�a�b�E�r�s�u�Q�ǂ��v���C���^�C���g�ł̏��ԑg����Ɉӗ~��R�₵�Ă������ŁA�ߌ�[���т̎��А���Ɏ��g�̂��������ł���B�ߌ�т̏��ԑg�͊��ɂg�a�b�E�r�s�u�ł����{����Ă������A�������͖k�C���V���̖L�x�ȏ�����p�������ԑg�̐�����Ӑ}�������̂ł���B�P�X�W�X�N�P�O���Q���ߌ�S����ɃX�^�[�g�����m�s�u�|�e�g�W���[�i���n�ł���B�X�ɓ��Ђ͂P�X�X�S�N�P�O���R������͌ߑO�т̏��ԑg�Ƃ��āA���g�a�b�A�i�̍����̂�䂫�����N�p�����m�̂�䂫�̃g�[�N�c�d�k�C���n�i���[���X�D�O�O�`�j��Ґ��������A���̔ԑg���Q�O�O�Q�D�P�P�D�P�P���ɂ͕����J�n�Q�O�O�O��𐔂��鎖�ƂȂ��B����ߌ�тɂ��Ă͂��̎��ԑт̏��ԑg�Ƃ��Ęb����W�߂��r�s�u�e���r�́m�ǂ����C�h�P�Q�O�n�������邱�Ƃ��o���悤�B���̔ԑg�͂P�X�X�P�N�P�O���V������ߌ�T������̂Q���Ԕԑg�Ƃ��ăX�^�[�g�������A�n���ǂƂ��Ăِ͈F�Ƃ������钷���Ԃ̏�ԑg�Ƃ��Ē��ڂ𗁂т����̔ԑg��'�X�R�N�P�O������́m�ǂ����C�h�Q�P�Q�n�Ƃ��čăX�^�[�g�����݂Ɏ����Ă���B���̎��ԑтɂ͂g�a�b�m�r�^�~���s�u�n�A�g�s�a�m�[���c�����I�c�����I�n�A�X�ɂ͂m�g�j�m�ق��ق��e���r�n�����А���̏��ԑg��Ґ������������e���r������Ȃ铬�����������Ă���B
���̂悤�Ɋ����̎������o�Ȃ���e�Ђ̒n����ԑg�ւ̎��g�݂́A���ݑS�������Ԃ̒��ł̎��А���̔䗦�����߁A�e���ԑтł�����ȃj���[�X�A���ԑg�̓������J��L�����A���̎��������d�g�L�������ɂ��傫�ȉe���͂��y�ڂ����ƂȂ����̂ł���B
�@
���{�o�ς͉~���s�����������ĂP�X�W�U�N�����炢���颕����i�C����n������̂ł��邪����̎����k�C���͂ǂ̂悤�ȏŐ��ڂ����̂ł��낤���
�P�X�W�O�N����X�^�[�g�������̍����Č�����ɔ����������Ɨ}����͖k�C���o�ς̒�ɔ��Ԃ������邱�ƂƂȂ�����k�C���̌o�ς��x���Ă���̂͌������ƂƊό��ł��褂��̖ڋʂł���������Ƃ̍팸�͋ɂ߂đ傫�ȑŌ���^�����̂ł��顉����ĂP�X�W�O�N�'�W�P�N�������'�W�R�N�Ƒ������_�Ƃ̗�ЊQ��P�X�W�T�N�ȍ~�̖k�m���Ƃ̌��D��S�|����D�Ȃǂ̊�Y�Ƃ̍\���s�����ɂ��P�X�W�O�N����P�X�W�T�N�̌o�ϐ������͔N����1.1%�ƑS������3.7%��傫������錋�ʂƂȂ����
�@�} 38�@�o�ϐ������̐��ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
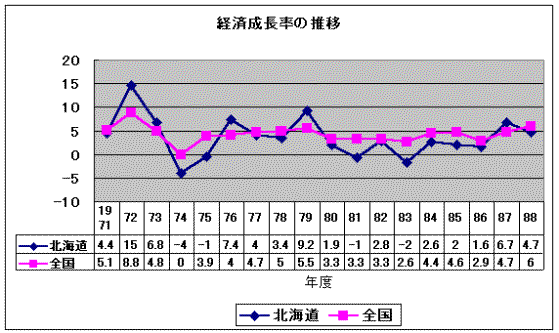 �} 39�@�����o�ϐ�����
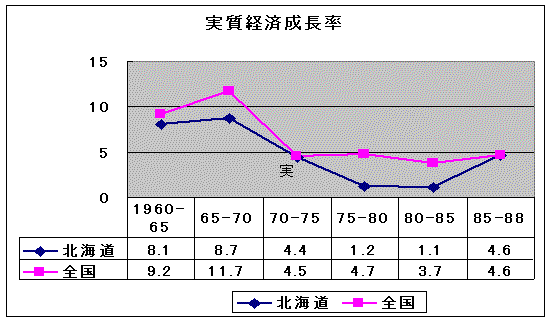 ��L�̎����Ɍ���@���P�X�W�O�N��̖k�C���o�ς͐��ň��̏ł������ƌ����悤��k�C���̎����o�ϐ������P�X�W�P�N�'�W�R�N��������}�C�i�X�����ƂȂ��Ă���̂͑O�q�̗l�ɂ��̔N�̗�ЊQ�ɔ����e������ꎟ�Y�Ƃ���łȂ��n��o�ςɑ傫�ȉe����^�������̂ƌ������Ƃ��o���悤�
�P�X�W�U�N�̉~���s���̔g�͖k�C���n��ɂ������������'�W�V�N�ȍ~�S���I�Ȍi�C�̉ƕ����ċً}�o�ϑ�ɂ��������Ƃ̑啝�ȑ����ɂ��ǖʂ̓]����}�鎖���o�����̂ł���
�k�C���o�ϔ����ɂ��Ƥ�P�X�W�V�N�k�C���ɓ������ꂽ�J�����Ɣ��10.991���~�Ɖߋ��ō��ł������O�N��2.9%�����^�Ȃ��̂ł�������������������͖{���ɉ����Ă͌i�C��Ƃ��č������ʂ������Ă�������������ŏI���v�ɐ�߂�傫�����l����Ɩ��Ԑݔ����ア���łP�X�W�V�N�̌i�C�̌����͂Ƃ��Ă̖����͋ɂ߂đ傫�Ȃ��̂�������������Ėk�C���o�ς��x���������̒��ł���ό����P�X�W�V�N�͑傫���L�т���������i�C�Ɍq����傫�ȗv���̈�ł��顂��̑��̌o�ώw�W�̒��œ��M�����̂͌��݊֘A�ł��褏��Ɨp�r�����݂͑O�N��11.6%�ƂP�X�W�P�N�̐����܂ʼn�������Z��H���͑O�N��25.6%�̑��ł��ꖒ�@�P�X�V�X�N�ȗ��̒��H�����L�^������Z��H�������̂悤�ɑ傫���L�т��̗v���̈�͎D�y���ւ̐l�������̑����ɂ�鐢�ѐ��̑����Ƥ����͎D�y�s�̑������n���S�̘H�������ɔ����Z��n�̊J�����������Ă��顖���i�C��i�߂��v���Ƃ��Čl����̊g���Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����̎w�W�Ƃ��ĕS�ݓX�ƃZ���t�X�����킹����^�����X�̔���グ���O�N��5.3%�ƐL�Ѥ�����ɂ����鎩���Ԕ̔��䐔���O�N��2.6%�ƐL�т�Ȃnji�C�͒����ɉ����ݎn�߂��̂ł��顁@�@�@�@�@�@
�@
�������܂Ŗk�C���̌o�ς��x���Ă����̂͏��X�̊J���v��ł��������P�X�T�Q�N�̑��������J�����ォ�琔���đ�U���̌v�悪���ݐi�s���ł��邪�A
����܂ł��f�ГI�ɋL�q���Ă�������U���v��̍���ɓ����荑�y��ʏȖk�C���ǂ��Z�߂������m�k�C���J���̉��v�n����~���E��ł��̗��j��U��Ԃ��Č������B
�@�@��P�������J���v�掞��i�P�X�T�Q�N�|�P�X�U�Q�N�j�ł͂P�X�T�Q�N�|�T�U�N���P���T�P�N�v��A�P�X�T�W�N�|�U�Q�N���Q���T�P�N�v��ƒ�߂��B��P���T�P�N�v��̖ڕW�́m�����J���n�œd���̊J���A���H�A�`�p�A�͐쓙�����g�[�A�H�Ƃ̑��Y���A����ɑ���Q���T�P�N�v��̖ڕW�́m�Y�Ƃ̐U���n�ŐV���ɍ��y�ۑS�A�_�ѐ��Y�Ƃ̐��Y���̌���A���������ݔ��̐������������A��P���v��ɂ�4,335���~�A��Q���v��ɂ�6,600���~�̎������\�肳�ꂽ�B
�A�@ ��Q�������J���v�掞��i�P�X�U�R�N�|�P�X�V�O�N�j�ł͊J���̖ڕW���m�Y�ƍ\���̍��x��]�Ɛݒ肵�A����𐄂��i�߂邽�߂̑����I��ʒʐM�̌n�̊m���A�Љ�����{�݂̐����g�[�ɏ�����̉�����鏈�ƂȂ��B�����v����啝�ɑ��z����3��3,000���~�ƂȂ����B
�B�@ ��R�������J���v�掞��@�i�P�X�V�P�N�|�P�X�V�V�N�j�̖ڕW�́m�����Y�E�������Љ�̌��݁n�ŁA�X�Ɍ�ʒʐM�G�l���M�[�̗A���̌n�̊m���A�ό��J���̐��i��搂�ꎑ���K�͂�20��7,500���~���v�コ�ꂽ�B
�C�@��S�������J���v�掞��(�P�X�V�W�N�|�P�X�W�V�N�j�ł́m���萫�̂��鑍�����̌`���n���J���̖ڕW�ɁA����܂ł̊�Ր������X�ɐi�߂鏔�{�v�悳�ꎑ���K�͂�47��1,000���~�ƂȂ����B
�D�@��T�������J���v��i�P�X�W�W�N�|�P�X�X�V�N�j�́m�䂪���̒����I�Ȕ��W�ւ̍v���A���̓��O�Ƃ̋����ɑς�����͋����k�C���̌`���n��ڕW�ɁA�_��Ŋ��͂���Y�ƌQ�̌`���A���x�Ȍ�ʁA���A�ʐM�l�b�g���[�N�̌`���A���S�ł�Ƃ�̂���n��Љ�̌`������v�Ȏ{��Ƃ��Čf��������������60���ɋy�B
�E�@��U���ق��ړ������J���v��(�P�X�X�W�N�|�Q�O�O�V�N�j�́A��T���v��ł͓������������ɏƂ炷�ƁA�l����o�ϐ������͌o�Ϗ�̕ω��Ȃǂ̗v���ɂ��K�����������ɐ��ڂ��Ă���Ƃ͌�����B�����̔��Ȃɏ�ɗ����ĐV�����Ή����K�v�ł���Ƃ̔��f����V�����J���v�悪���Ă�ꂽ�B
���̂悤�ȍ��̎{��ɑΉ����Ėk�C�����Ǝ��̌v�悪���肳��A�悸�P�X�V�W�N�ɂ͂P�O�P�N�ɋy�ԁm�k�C�����W�v��n�����{���ꂽ���A�P�X�W�V�N�P�P���ɂ́m�k�C���V���������v��n�����肳�ꂽ�B���̌v��͂Q�P���I��W�]���āA�@�k�����ƃA�W�A�A�����m�n������ԋ��_�A���������n�搶���o�ό��B�_�C�i�~�b�N�Ȕ��W�͂����Y�ƇC���S���ďZ�߂�ӂꂠ���̎Љ�D�l�ԂƎ��R�Ƃ̋����E�V�����l�b�g���[�N�A����炪�V�����ڕW�Ƃ��Čf����ꂽ�B���̌v������{����ɓ������Ă̌���F���Ƃ��Ď��̓_���w�E����Ă���
�P�D.�o�ϐ������̓݉��P�X�W�O�N�ȍ~4�N�Ԃ̖k�C���o�ϐ������͑S�����ς̔����̐����ł��顖���z�H�Ɛ��Y��ٗp�ʂ̎w���͑S��9�u���b�N�̍Œᐅ���ł���
�Q�D.�Y�ƍ\���̓]��
�@�@�k�C���̎コ�͍H�ƒ~�ϗ͂ɂ��顂������������邽�߂̎Y�ƍ\���̓]�����K�v�ł���
�R�D.��������l��
�@�@�P�X�W�O�N�ȍ~�̐l����������1.9%�ɗ��܂��Ă��褐l�������̎s�����͑S�̂�80%�ɋy��ł��顂P�X�W�U�N�̐l���͑O�N��}�C�i�X�ƂȂ����
���̗l�Ȍ���F���Ɋ�Â���L��10�P�N�̑����J���v�悪���{����鎖�ƂȂ�A�O�q�������X�̖ڕW���ݒ肳�ꂽ���A��̓I�ɂ͑�����ɘj����21���I�Ɍ����Ėk�C�������������邽�߂̃v�������v�悳�ꂽ��헪�v���W�G�N�g�Ƃ��Ĥ��q��F���Y�Ɗ�n���_�ƒn��Y�ƕ������_���C�m�J�����_���ՐX�ь^�s�s�����ۃG�A�J�[�S��n�����ۃ��]�[�g�A�_�s�s��������ʃV�X�e�����n��v����V�X�e������Õ���INS����X�P�[���̑傫�Ȍv�悪�ł��o���ꓹ���̖�����̂ł��邪������ɓ���o�u���o�ς̕���ケ���̃v���W�F�N�g�����̌v�悪��������铙�A�v�挴�ĂƂ͈�����p�Ő��ڂ��Ă���
���̂悤�ȊJ���v��Ƃ͕ʂɖk�C���ɂƂ��Ă̍ő�̘b��͢���g���l����̊J�ʂł��顂P�X�W�W�N�R���P�R�����I�̓�Ƃƌ���ꂽ���g���l�����J�ʂ���{�B�Ɩk�C���̓g���l����ʂ��ė������ƂȂ蕨���Ȃnjo�ϖʂł̔g�y���ʂ͑傫���������̔N7���Q�O���ɂ͐V����ۋ�`�������H����A�����H��������^�[�~�i���r�����P�X�X�Q�N�V���������V���ɊJ�Ƃ������C���̃A�N�Z�X�̏[���͍���̖k�C���o�ςɐV���Ȋ��H�ݏo�����ƂȂ�������������̔N��P�X�W�W�N�U���R������P�O���R�O�����D�y�������J�n���ʉ��Ɣ��ى��Ŏ��{���ꂽ��H�̍ՓT��͖k�C���S��ɘi��C�x���g�Ƃ��ē��哱�œW�J���ꂽ�����ʂ͑傫�ȕ��̈�Y���c���ďI������Ƃ����㖡�̈������ʂƂȂ����̂ł���
�@
�S�����x���̍L����ڂ�5-1�ŏq�ׂ��ʂ�ł��邪����̎��㌵�����o�ϊ��ɔ����ꂽ�k�C���n��ł̍L����͂ǂ̂悤�ɐ��ڂ��ė����̂ł��낤���
����܂ŋL�q�����ʂ褍L���E�ɂƂ��đ傫�ȑŌ������P�X�W�U�N�̑S���}�̕ʍL����̐L�ї��͐V��102.9%����W�I101.3%��e���r102.6%�Ƃ�����̔}�̂��������ɏI�n�����̂ł��顓���'�W�U�N�k�C���n��}�̂̐L�ї��͐V��109.1%����W�I101.3%��e���r102.6%�ƐV�����ˏo�����L�ї����������̂ł��顂����ė�'�W�V�N�͈�]���ĐV�����O�N�����98.8%����W�I102.7%��e���r110.9%�̐L�ї�������������k�C���n��ł̂��̂Q�N�̐��ڂ��ǂ̂悤�ɕ��͂��ׂ��Ȃ̂�����f�ɋꂵ�ނ̂�'�W�V�N�ɂ͌o�ς��D�]�̒�����������S���L������V��108.2%����W�I105.8%��e���r107.7%�Ə����ȉ������Ă���̂ɑ���k�C���n��ł̐V���L����݂̂��P�X�W�U�N109.1%��W�V�N98.8%�ƓƎ��̓����������Ă��邱�Ƃł��顂��̖ʂɂ��Ď��͎��̗l�ɕ��͂��Ă��顖k�C���o�ς͂P�X�W�P�N�ȍ~�s���Ɍ�����ꂽ���A�P�X�W�V�N�̐��{�ً̋}�o�ϑ�ɔ�����^�̌��������ɂ��ǖʂ̓]����}�鎖���o��������������̌i�C���������Ƃ𒆐S�Ƃ������������Ɏx�����Ă̐������ł��褓����̎��̌o�ς͒n��Y�Ƃ̒��ő傫�Ȕ�d������O���Y�Ɠ��̌i�C�͖{�B�Ɣ�r����2�N�̃^�C�����O������ƌ����Ă��顒n���i���͂P�X�W�U�N���͂ނ���W�V�N�ɕs���̂������������̖ʂŒn���V�G�A�̍����V���L����ɂ��̂܂ܒ��˕Ԃ����̂ł͂Ȃ��낤������̓_���猾���Γd�g�L���邏��Ƀe���r�L����͓��O����̍L�������̈ˑ��x�������S���̌i�C�ϓ��ƋO����ɂ��Ă��褂��̎�����L����̐L�ї����S���Ɠ������ڂ������Ă���Ɨ������Ă��顂�����ɂ���n��V�G�A�̍����V���L���裸����ˑ��x�̍����e���r�L���車��̔}�̂̎��c�Ɠ��������̔N��̔}�̍L����̗���ɑ傫�ȕω��������炵���̂ł���
���̗l�ȏɊ֘A���Ėk�C���V����30�N�j�̋L�q���Љ��
��L30�N�j�ɂ��Τ���ЍL���������P�X�W�R�N����A��3�N�ɘi���đO�N���ъ�����L�^�����͖̂k�C���V���L���j�㏉�߂Ă̎��ł��褂��̊��Ԃ͋L�^�I�t���̊��Ԃł������Əq�ׂĂ��顂��̌X���͓��������̌X���œ��O�x�Ђ͏����ɐ��ڂ��Ă���Ƃ��q�ׂĂ���
�k�C���V���̍L�������ͤ��L30�N�j�ɂ��P�X�V�P�N�̍L��������100�Ƃ����ꍇ��P�X�W�T�N349.9��P�X�W�W�N434.5�̐L�тƂȂ��Ă���B�P�X�W�R�N����P�X�W�T�N�܂ł͑O�N�}�C�i�X�ƂȂ������̂́A�P�X�W�W�N�͑O�N�ɔ�ׂ�55.7�|�C���g�̑����������Ă��褂P�X�W�W�N�ȍ~�P�X�X�O�N��ɓ����Ă���̓��V�̖��i�U����M�킹�Ă���̂ł���
�P�X�W�O�N��̖k�C���n��L����ڂœ��M���ׂ����́A�e���r�L������̔N��ŐV���L�����ǂ������e���r�L���哱�^�̗������������ł��顂P�X�V�T�N�S�����x���Ńe���r�L����V���L����𗽉킵�Ĉȗ������ɒx��鎖10�N�e���r�W�҂̔O��������鎖���o�����̂ł��顎c�O�Ȃ��ƂɂP�X�W�P�N�܂œd�ʖk�C���x�Ђ��Z�肵�Ă�����k�C���L����裂��P�X�W�Q�N�ȍ~�쐬���ꂸ��P�X�W�T�N�ȍ~�͓d�ʖ{�Ѝ쐬�̢���{�̍L����G���A�z������쐬���ꂽ��]���ĂP�X�W�Q�N��W�R�N��W�S�N�̖k�C���n��}�̕ʍL����s���̈פ�e���r�L������m�ɉ����̎��_�ŐV���L����𗽉킵�����͒肩�ł͂Ȃ����P�X�W�T�N���_�Œǂ��z�������͎��̃O���t������������̂ł���
�}�@40 �k�C���n��}�̕ʍL������z
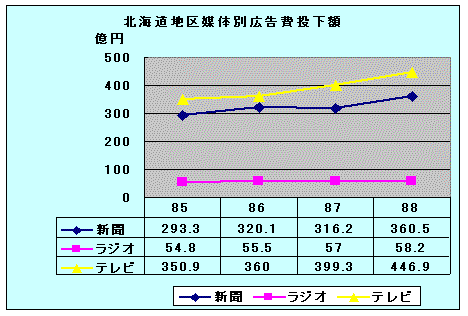 �@ �@�}�@41 �k�C���n��}�̕ʍL����V�F�A
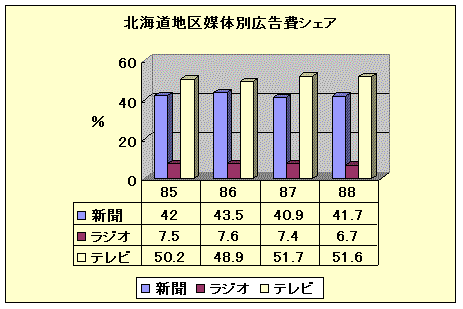 5-5��k�C��������o�ϊ���ŋL�q�����ʂ褂P�X�W�O�N�O���̖k�C���o�ς͐��Œ�ƌ�����ɂ���������̎����L����̖ʂł��n���V�G�A�̍����V���L����ɑ傫�ȑŌ���^������ʂP�X�W�O�N�N��㔼�͏�}�Ɍ���@���e���r�L������嗬�Ƃ��Đ��ڂ������A�S�ʓI�ȓ����Ƃ��Ďw�E�ł���͎̂G���L����̑䓪�ł��낤��P�X�V�T�N�ȍ~�D�y�s��𒆐S�Ƃ����o�ł̏ɂ��Ă͑O�q�����ʂ�ł��邪��P�X�W�T�N�G���L����͓����z�ɂ����ă��W�I�L���������̓����z���P�O�N�O�ɔ�r���ĂQ�O�{�ȏ�̍L����������Ă��顏�̃O���t�ł͖k�C���n��̐V������W�I��e���r�L����V�G�A���L�ڂ�������V���͂P�X�V�O�N��㔼�܂ł͏��50%�𒆐S�ɐ��ڂ��Ă������P�X�W�O�N�ȍ~40%�O���ւƃV�G�A�_�E�����Ă��顑����ăe���r�L����V�G�A��50%��(�P�X�W�U�N������)����V�G�A���m�ۂ���Ɏ���������V���L���Ɛ莞�ォ�烉�W�I��e���r���̓d�g�L���̏o����d�g�L���̐�������W�����o�ēd�g�}�̂̓e���r4��(�P�X�W�X�N5��)����W�I3��(�P�X�X�R�N4��)�ƌ����d�g�L���̐��n�����}���L���s��͊����������f���ȂǑ����f�B�A������ȓ����𑱂��Ȃ��珺�a���畽���ւƃo�g���^�b�`���顕���������}�����L���ƊE����Ƀe���r�ƊE�͉q������̖{�i�I������҂��ƂȂ������ʐM���܂߂���]�������}���鎖�ƂȂ�
�O�i�łP�X�W�P�N����P�X�W�S�N�̓d�ʂɂ�钲���������쐬����ĂȂ������q�ׂ����A�P�X�W�O�N��㔼�ɂ����Ă͒n��L����̖ʂł̓e���r�̐L�т����M�������̂́A�n���L����ɂ��Ă͐V���L����D���͕̏ς���Ă��Ȃ��B4-7�k�C����v�G���A�ʍL����̍��ł͂P�X�V�P�N����P�X�W�O�N�܂ł̒n���L����ɂ��ďЉ�����A�d�ʂ̎������Ȃ��P�X�W�Q�N����P�X�W�S�N�̒n���L����ɂ��āA���V����̐��������Д��s�̔N�ӂɋL�ڂ���Ă���̂ŏЉ��B�A������͐V���E�d�g�̓�敪�ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�ʁ@���~ (�@)�͑O�N��
�@
����܂ł͓d�ʂ�[���{�̍L����]�𒆐S�ɍL����������Ă������A�{�͂ł͎��_��ς��ĂP�X�W�O�N��I�Ղ̃e���r����W�I�̍L������c�Ǝ����Ƃ����ʂ��猟�����̓��Â͂��鎖�Ƃ��顑O���ł͊e�Ǖʂ̎����ɂ��Ă��̐��ڂ����������A����͍L���s��𒆐S�l���A�e�Ǖʂ̎����ɂ͌��y�����A���W�I�A�e���r�Ȃǃ��f�B�A�ʂ̑������ɂ��Č����鎖�Ƃ������B
�P�X�V�Q�N�ɖk�C���n���l�ǖڂ̃e���r�ǂƂ��Ėk�C�������������J�ǂ��k�C�����{�i�I�Ȓ����l�c�g���[�N�Ɍq����l�n��̐����m�����������P�X�W�Q�N�ɂ͖k�C���n���O�ǖڂ̃��W�I�ǂƂ��ăG�t�G���k�C�����J�ǂ����
�}�@42 �k�C���n��d�g��������
�@
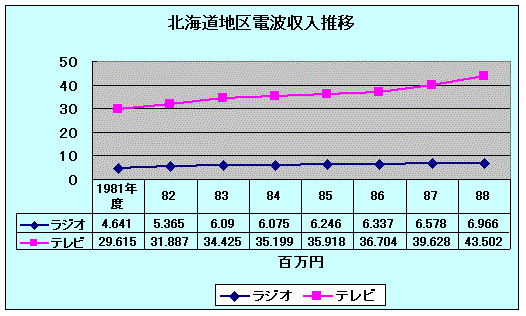 �@
��̃O���t�͖k�C���n��̓d�g�����̐��ڂ����������̂ł��邪�A�e���r�����P�X�W�W�N�x�̎��т͂P�X�W�P�N���P�O�O�Ƃ���ƂP�S�U�D�V������W�I�����͂P�T�O�D�P�̐L�т������Ă���A�P�X�W�S�N����P�X�W�U�N�ɂ����Ă̕s�����l����Ə����ɐL�т��ƌ�����̂ł͂Ȃ��낤����A�����W�I�����ɂ͂P�X�W�Q�N�J�ǂ���FM�k�C���̎�����������Ă̎����ł��顎��Ƀe���r�X�|�b�g�ɂ��Č����邪�A���5-2��e���r�L����̎���I�ω���őS�����x���ł̃X�|�b�g�d���̗���ɂ��ēd�ʎ������Q�l�Ɍ���������k�C���n��̎��тɂ��Ă������ʂ��猟���鎖�Ƃ���
���y�[�W�̃O���t�͂P�X�W�T�N�x����P�X�W�W�N�x�̖k�C���n��e���r�ǃX�|�b�g�������т̐��ڂł��顃e���r�S�����ɐ�߂�X�|�b�g�����̃V�A�����Ă��P�X�W�T�N�A�W�U�N��50.4%�A�W�V�N52.8%�A�W�W�N53.9%�ƁA�N���ɂ��|�g�̃V�F�A�A�b�v�̎��Ԃ����炩�ɂȂ����B���̂悤�Ȑ��ڂ�����ɂ��A�k�C���n��ɉ����Ă��X�|�b�g���e���r�����̎嗬�ƂȂ褍���v�X���̌X�������߂鎖���z�肳���̂ł���B
���ɃX�|�b�g�����̒n���(���O�����)�V�G�A�������鎖�Ƃ���
�P�X�W�U�N��W�V�N�x�͖k�C���o�ς����Œ�ƌ����ŗ���������ł��褏]���ăX�|�b�g�̐L�т͓��O�����z�Ɉˑ�������Ȃ��ɂ������
�P�X�W�W�N�x�͓����i�C�̉ɔ����ē��������z�V�F�A��������̌X���ɓ]���邪����㕽������ǂ̂悤�Ȑ��ڂ�H�邩�𒍈Ӑ[�������K�v�����낤�
�}�@43�@�k�C���n��n��ʃe���r�X�|�b�g����
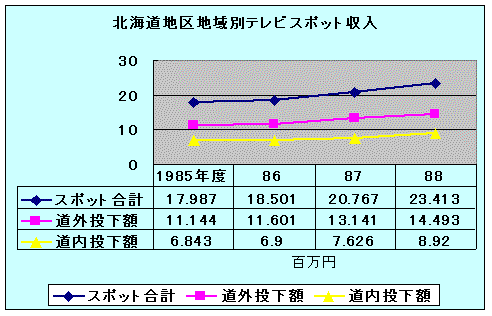 �@�@�@�@�@�@�@
���ɖk�C���n�惉�W�I�ǂ̎����ɂ��ĕ��͂��Ă݂����B
���L�̃O���t�͓������W�I�O�ǂ̎����̐��ڂ��������O���t�ł���B�@
�@
�}�@44�@�k�C���n�惉�W�I�������ځ@
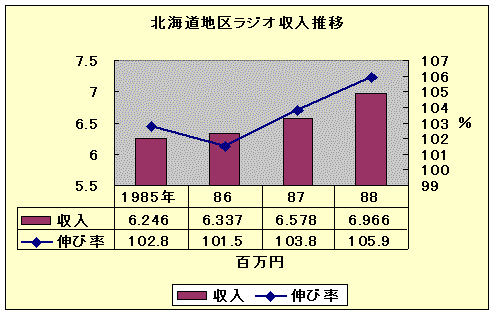 �@ �@�@
�O�f�̃O���t�ł��������悤�ɂP�X�W�O�N��̏I�դ�P�X�W�T�N����W�W�N�̖k�C���n��ł̐V������W�I��e���r�̃V�G�A�̓��A���W�I�͂���܂ł�3%�䂩��7%��ɃV�G�A��L���Ă������A�W�W�N�ɂ̓V�G�A��6%��ɉ��~���Ă��荡�㕽���ɓ����Ăǂ̂悤�Ȑ��ڂ�H�邩�����ɂ߂�K�v�����낤�
�k�C���̃e���r�L������K���P�X�W�O�N��̌㔼����V���L����𗽉킷�鎖���o�������A����Ƃ��}�X�R�~4�}�̂̒��Ńg�b�v�̍���ێ�����S�����̃V�G�A���L�[�v���Ă������߂ɂ͑����̉ۑ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��
���̈�͑ΑS���V�F�A�̖��ł��顔N�X�X�|�b�g�L����̖k�C���n��V�G�A���ቺ���钆�ŋ��͂ɐ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͑O�q������G���A�}�[�P�b�e�C���O��̓W�J�ɂ�铹�O����̃X�|�b�g�����z�����߂鎖�ł��顂���ɂ͖k�C������s��̊��������K�v�����ɂȂ邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ����ł��邪�����̍L�挗�ɂ�����}�[�P�b�e�C���O�헪�̓W�J����ł͂܂��܂��̔����������ł��铹������̂ł͂Ȃ��낤����X�ɂ���ƕ����ďd�v�ȓ_�͓����s�ꂩ��̓����z�V�G�A�����߂鎖�ł��顂��̂��߂ɂ͎������Ώd�̉c�Ƃ��王�_��ς��A���f�B�A�~�b�N�X�ɂ����W�J��̔��Ɍq�����̑���擙�X�̉c�ƊJ�������߂��ė��悤������ɂ��Ă�5-3�ŏЉ�������|�[�g���傢�Ɏ����ɕx���̂ƍl���Ă���B����̃f�W�^���q�������ɑΏ�����n��g�̎��g�݂Ƃ��Ă��A�X�|�b�g�}�[�P�b�e�C���O�ɑ���₦���錤���Ƃ�����c�Ɗ����ɋ�̓I�ɔ��f���Ă������H�����������g��̈�̃|�C���g�ɂȂ�ł��낤�
|