第三章 電波広告の成長期
1961年ー1970年(昭和36年ー昭和45年)1950年代は、数量景気から神武景気へと景気の上昇局面が続きこの時期にスタートした民放産業はこれら景気に支えられ、特にテレビ広告費は急速な成長路線を走り続けたのである。
1960年代は日本経済も1950年代前半の岩戸景気から一転して景気の後退局面に入り、1962年の実質GNPは一挙に6.4%に低落した。しかし1963年には翌'64年開催の東京オリンピックに関連して景気も上昇気流に乗ったものの大きな盛り上がりを見せないまま、いわゆる「好況感なき景気上昇」を経て1960年代後半に突入する。1964年4月には日本もOECDへの加盟が認められIMF8条国となるなど日本を巡る国際的な経済環境も大きな変化を迎える時代でもあった。景気の局面も1965年10月の不況期を脱して以降第6循環期にあたる「いざなぎ景気」に繋がり、1970年7月まで57ケ月続いたが、この間の実質成長率は驚く無かれ71.9%(年率換算で12.1%)を記録したが、この実績が全体の底上げとなり1966年から1970年までの実質GNP成長率は10%を超え5年間の平均成長率は11.6%に達した。しかしこの間景気が高度成長期にあったとは言え、1965年発生した山陽特殊鋼の倒産、山一証券への緊急融資など国内の経済不安が続く中、対外的にはニクソンショック、オイルショツクなどが加わり'65年不況はGNP成長率を前年の10.6%から5.7%へと後退させたのである。
小原 博氏(拓殖大学教授)は氏の著書[日本マーケッテイング史]の中で、1965年以降の[いざなぎ景気]を戦後の第二次高度成長期と位置づけており、この景気は[財政・輸出主導型]と定義付けながらその要因として色々な側面を挙げているが、我々にとって関心の深いマーケッテイングとの関連に於いては[高度成長の諸要因の内、技術革新の進展により新しい商品が生みだされたこと、これが大量の需要を新たに創造したこと]を力説されている。高度成長の推移を比較したのが下の表であるが、国民総生産、国民所得、輸出の増加の推移を理解頂けよう。(経済企画庁30年史の統計)
図12 経済成長の推移 経済企画庁の[国民所得統計]を参照
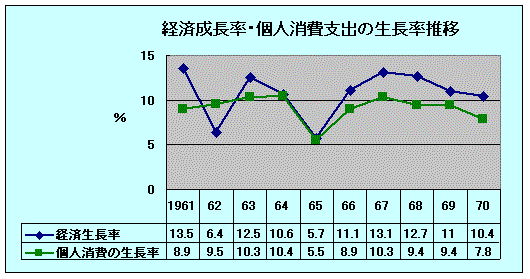 経済の高度成長期を迎えたが国民の個人消費支出についても時代と共に変化が見られるが、戦後の食糧難時代個人消費の中心は飲食費であった。
図13 個人消費支出の比較 大川一司氏著[個人消費支出]より引用
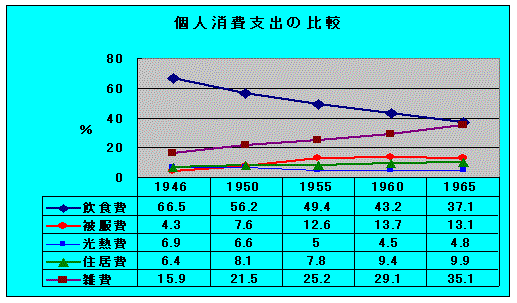 図13は大川一司氏著の[個人消費支出]のデーターを引用させていただいたが、終戦直後の1946年の全支出に占める飲食費の割合は66.5%であったものが、1965年にはその割合は37.1%迄下がり、代わって雑費が1946年の15.9%から1965年には35.1%に上昇している。時代と共に飲食費の比率の減少と、雑費の増加傾向が顕著となつたことが窺える。
前述した小原 博氏はこの現象を次のように解説している。[神武景気により高度成長の波に乗った我が国経済は、そこに働く人々に所得の大幅な増加をもたらすことになったが、戦前からの生活洋風化を更に強めて、誰もが生活近代化、高級化に向けて、衣、食、住すべての領域にわたって、特に家庭内の生活用具の購入、更にはレジャーの為に支出することにひたすら消費意欲を掻き立てたのである。そして昭和30年代の[三種の神器](白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)、昭和40年代の[3C](カラーテレビ、クーラー、カー)の購入ブームが到来して従来の消費構造を大きく変え、国民生活が大きく変化した]。これを裏付けるのが下のグラフであるが、消費者の購買意欲を刺激して大量消費時代を作り上げるため電波広告の果たした役割は極めて大きなものがあった。
図14 主要耐久消費財普及率推移 経済企画庁[消費動向調査年報]1991年
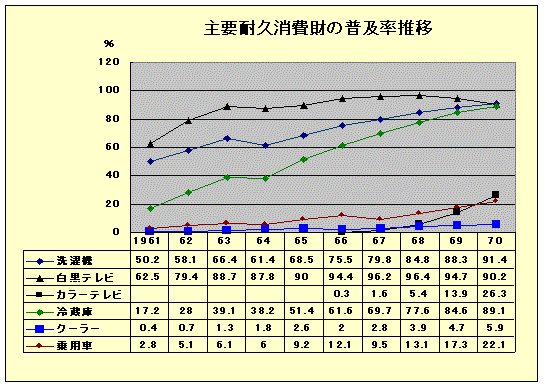 このような消費の高まりを受けて広告に対する問題点についても議論が高まる中、1970年<第三次国民生活審議会>は広告に関する現状と問題点を指摘しているが、その答申の中から関連する部分について引用する。
先ず広告の現状について[我が国の総広告費は、経済規模の拡大にともなって増大し、1969年では、電通推計によると約6.328億円で、国民所得の1.3%を占めている。企業の売上高に対する広告宣伝費の割合は、製造業では医薬品、化粧品、食料品、精密機械などの非耐久消費財産業が最も
高く、ついで電気機器、自動車などの耐久消費財産業となっている。また、これらと並んで映画、百貨店などの第三次産業も広告費率が高い。
媒体別広告費を見ると、新聞、雑誌、ラジオ、テレビのいわゆるマスコミ4媒体で総広告費の約80%を占めている。]
次ぎに広告の問題点として、広告の内容、広告の表現技術、広告の量、広告の責任の所在をあげ、広告主の自主規制、広告代理店の自主規定、媒体の自主規定などが存在するもののその運用上の問題点を指摘している。電波関連については[日本民間放送連盟放送基準]の他、各社が独自の放送基準を設け規定としては比較的整っているものの、放送時間の制約などにより事前のチエックが十分行われない場合もあると指摘している。
この面に関しての道内民放各社の対応について述べてみたい。道内各社とも独自の放送基準を制定し、その中で広告についても民放連基準を準拠した規定を設けている。HBCは1957年7月1日[北海道放送放送基準]、STVは1959年3月28日[札幌テレビ放送番組基準]、HTBは1968年11月3日[北海道テレビ放送番組基準]、uhbは1971年11月10日[北海道文化放送放送基準]、TVhは1988年6月21日[テレビ北海道放送番組の編集の基準]を制定し、各社とも[広告は真実を伝え視聴者に利益をもたらすものでなければならない]と広告放送の基本原則を明確に規定した上で、広告の取り扱いの細部について、広告の表現、医療・医薬品・化粧品などの広告、不動産の広告、広告の放送時間の基準、等を規定し視聴者からの信頼を得る広告放送の実現に努力が払われている。
このように広告が国民生活に大きな影響力を持つようになった要因の一つは、民間放送の歴史の経過と共に放送コマーシャルが生活面でも大きな役割を果たしつつある証左というべきであろう。
このような好景気により1960年代の広告費はどのような状況で推移したかを検証することとする。
日本の広告費(電通)によれば1961年(昭和36年)の日本の総広告費2.110億円は1970年(昭和45年)には7.560億円と実に3.6倍の大きな伸びを見せたが、一方この間の実質経済成長率も年平均10.2%という高い成長を遂げたため国内総生産に対する総広告費の比率は1961年の1.09%から1070年には1.03%に留まっている。
1965年には日本経済も不況期に直面し、総広告費でも史上初めて前年比98.5%となり、メイン媒体である新聞広告費は前年比95.1%、ラジオ広告費前年比94.7%といずれも前年割れを余儀なくされたものの、独りテレビ広告費のみが前年比102.7%と辛うじて前年実績を維持することが出来、テレビ広告の持つ媒体力が改めて見直される処となったのである。
このことはテレビ広告費の伸び率を見ても1961年の539億円が1970年には2.445億円と実に4.5倍の伸びを示しているのに対し、ラジオ広告費の伸びは1961年の178億円に対し1970年には345億円と約2倍の伸びに留まったが、テレビの成長と反比例して年々低成長を余儀なくされたラジオが1060年代後半には新しい媒体戦略により低落傾向に歯止めをかける一つの転機を作った。このことは後程検証することとしたい。
今まで述べたことを具体的な数字で検証するために電通資料を基に1960年代のわが国広告費の推移を新聞・ラジオ・テレビのメイン媒体についてグラフで表示する。
図 15 全国メイン媒体広告費推移
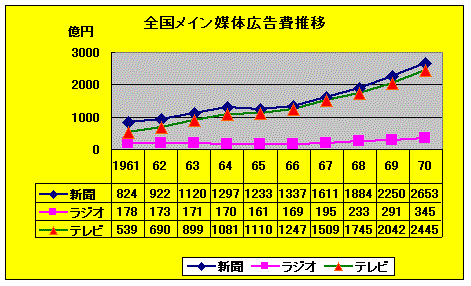 上記のグラフが示す通り、1960年代は新聞広告費・テレビ広告は概ね順調に推移して来た。一方ラジオ広告費は1959年テレビ広告費に逆転されて以降厳しい状況で推移して来たが、1965年のラジオ業界挙げての巻き返しキャンペーンが功を奏し、1967年以降順次業績の回復に向けて動き出したのが一つの特徴であろう。
叉、1961年時点では総広告費に占める新聞・テレビの媒体シェアは新聞39.1%に対しテレビ25.5%と13.6%の開きがあったが1970年には新聞35.1%、テレビ32.3%と其の差も2.8%とほぼ接近状態になり、この傾向が1975年の新聞・テレビ広告費の逆転現象に繋がる事となるのである。
1959年テレビ広告費に追い抜かれた以降苦しい局面で推移してきたラジオ広告費は、1965年を底として1966年に回復し、その後上昇気流を走り続けた。1965年の不況によりラジオ広告費も前年割れを余儀なくされ、ラジオメディアの先行きに暗い影を投げかけメディアに携わる全員に厳しい危機感が漲ったのである。商業放送の先進国アメリカでは情報メディアとしてのラジオが高く評価され、テレビ時代におけるラジオの持つ有用性が地域メディアとしての市民権を獲得していた。1965年4月アメリカRAB(ラジオアドバダイジングビューロー)会長エドマンド・C・バンカー氏が来日し、各方面での講演会等を通じラジオの未来展望についてわが国関係者に大きな希望を与え、これを契機にわが国のラジオ業界全体が一丸となってラジオメディアの復権に向けてのキャンペーンがスタートした。同年10月には民放連にラジオ強化委員会が発足し、具体的ラジオキャンペーンが全国ラジオ局において展開されたのである。
一方この様な業界挙げての回復への努力を強力に支援するような社会状況が着々と整えられつつあった時代背景もラジオ復権への大きな支えとなっていたのである。種々の要因が挙げられるが、ラジオを支えた大きな力の一つとしてカーラジオの普及を挙げる事が出来よう。
わが国の乗用車生産は1950年の朝鮮戦争による特需景気を背景に急速な回復を見せ、窮乏した生活から立ち直った人々の間には自家用車を持つと言う大きな夢が現実化される様な状況を迎える。
 特に1958年発売された大衆向け軽自動車「スバル360」はこの機運を大きく盛り上げ、各メーカーも挙って量産体制に入り、1966年には「カー・クーラー・カラーテレビ」が「新三種の神器」と呼ばれる年になったのである。 特に1958年発売された大衆向け軽自動車「スバル360」はこの機運を大きく盛り上げ、各メーカーも挙って量産体制に入り、1966年には「カー・クーラー・カラーテレビ」が「新三種の神器」と呼ばれる年になったのである。この事に関して佐藤正明氏は著書[ホンダの神話]の中で次のようにコメントしている。[三Cの花形商品は、誰が見ても自動車だつた。"マイカー元年"の前夜にあたる1965年の日本の自動車の生産台数は187万台だったが、五年後の1970年には529万台と2.8倍も伸びた、この間乗用車は70万台から318万台へ4.5培も増加している、日本の自動車産業の成長は明らかに乗用車、それもマイカーを中心とした自家用車によってもたらされたと言える。……乗用車が大衆の物となり、自動車メーカー各社はオーナードライバーを狙って次々と新車種を発売して商品の多様化を図りながら、既存車種のモデルチエンジを繰り返して市場開拓に努めた]。1966年にはトヨタ自動車の「トヨタカローラ1100」が発売され、翌1967年には東洋工業(マツダ)から世界で初めての小型軽量、高出力のロータリーエンジン搭載のスポーツカーが発売、叉1968年にはいすず自動車から高性能のDOHCエンジン搭載の車が発売されるなど、消費者の購買意欲を高める新機種が続々と開発され、年々自家用車の保有台数も鰻登りに増加の一途を辿り、この面からも車とラジオの関係が再認識されるに至った。将にモータリゼーションの到来はラジオにとって神風的存在となったのである。この事は北海道における乗用車台数の統計にも如実に表れている。北海道陸運協会編「北海道自動車統計」によれば、北海道での乗用車は戦後の1946年僅かに649台に過ぎなかったがその後1955年4.167台、1961年には18.256台に増加し1965年に入ると一挙に79.276台に増え、更に1970年には361.395台と5年間で455.9%の伸びを示したのである。これら増加の大きな要因は可処分所得の増加は勿論であるが、国内各メーカーの新機種開発と激しい販売競争がこれに拍車をかけたと言っても良いだろう。加えて家庭における生活様式の変化は住宅事情の改善と共にラジオが個人のコミュニケーションツールとして若者を中心に浸透する環境を作るなどこれまでのラジオ聴取対応にも大きな変化をもたらした。叉、送り手である放送局サイドも聴取者の変化に合わせて「オーディエンスセグメンテイション」いわゆる聴取者細分化方式等極め細かな編成方針を採用した。
先ずラジオ先発社であるHBCラジオは1967年5月1日ラジオ深夜放送[北海道26時]をスタートしたが、2年後の'69年6月2日からはオールナイト放送として[オールナイトほっかいどう]を開始した。終夜放送の流れはキー局を中心に始められており古くは1959年10月のニッポン放送よって始められ1967年7月1日のTBSラジオによって東京ラジオ全局が終夜放送となった。道内ではSTVラジオが1970年9月から[アタックヤング]の放送を開始した。深夜放送が主としてヤング聴取層をターゲットとしているのに対し、聴取者の生活慣習の変化と、カーラジオの急激な増加に対応すべく土曜、日曜の番組編成にも大きな変化が見られた。HBCラジオが1970年5月16日から土曜の午後帯に[ダイナミックサタデイ]を、又、1971年5月16日から日曜の午後帯に[サンデーワイド ナマナマ大作戦]を編成し、スポンサーの販促活動と一帯となった生ワイド番組で多くの話題を提供した。遅れてSTVラジオも1984年10月からは[河村道夫の桃栗三年][日高晤晤郎シヨー]を開始し、生ワイド番組はラジオ放送の核として定着する処となった。
このような広告メディアとしてのラジオをより積極的に利用して貰う手段として聴取者参加型の生活情報を重視した結果、ラジオ広告は地域性、費用対効果、販促効果などの面での評価に繋がったが、一方営業活動の面でもラジオスポットセールスに当たっては、'60年代に導入された「リーチアンドフリケンシー」の科学的手法による広告主、代理店に対する啓蒙活動に努力が払われたのである。このような様々な努力が実ってこの後ラジオメディアは'60年代後半の回復局面から拡大局面へと進み、1970年終盤には待望の一千億円ライン突破を果たす事となったのである。
最初に1960年代日本経済が順調に推移する中で北海道経済はどのような姿で推移してきたかを経済の幾つかの指標をもとに全国との比較で見てみたい。
図 16 北海道の経済水準
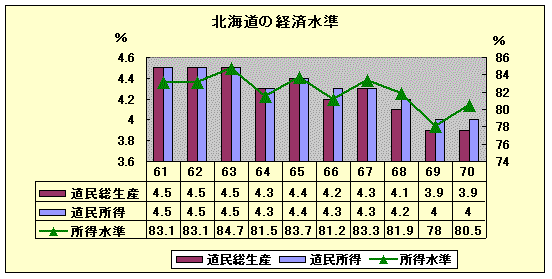 1960年代は道民総生産、道民所得の対全国比でも概ね4%を維持してきた。しかし所得水準では全国比80%台で北海道民の所得水準が全国水準に照らしても低い事が浮き彫りにされた。又、1960年代は北海道も第二次開発計画が進められる中、産業基盤の整備を中心とする人口増大政策の推進により人口も年々増大の傾向を示した。1960年の国勢調査における本道の人口は5.039.206人であったが1965年の同調査では5.171.800人、1970年には其の数も5.184.287人と10年間の人口増加数は145.081人であるのに対し札幌市の人口は1960年の615.628人が1970年には1.010.123人と100万人を突破しわが国で8番目の100万人都市の仲間入りを果たす事となった。 この様な人口の増加と共に産業構造の変化も見逃すことが出来ない。下の図17、18は札幌市の産業別就業者の推移を示したグラフであるが、札幌市においても時代と共に順次第一次産業から第二次産業、第三次産業へと傾斜する傾向が顕著となり、特にサービス産業を中心とした第三次産業が大きく伸びて来つつある。
図 17 札幌市の産業別就業者数
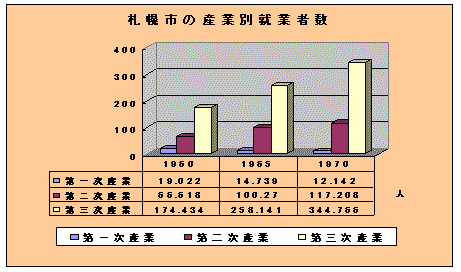 図 18 札幌市の産業別就業者数構成比
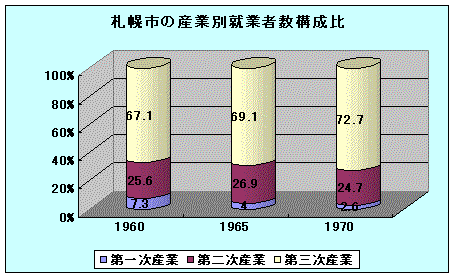 このような札幌の経済的発展は各種の統計資料にも見られる処であるが、1968年の札幌市の商業統計によると市の小売店数は9.168店舗で1966年に比較して9.3%の増加を見た。1962年を100とすると43.2%の伸びであり、市の人口もこの間42.1%の伸びで人口の伸びとほぼ同じ伸びを示しているのである。小売店数の伸びについては全国平均の統計では1966年に対し1968年の伸び率は1.0%であるが、札幌市は全国平均の約9倍の伸びとなり、全国都市の中では横浜に次ぐ伸びを示していて、札幌市の商業が急速に伸びてきた事を如実に物語っている。
1968年7月1日現在の札幌市の商店数は17.557店舗で、小売店数9.168は商店数の52%を占めており続いて飲食店数が30%、卸売り業が18%となっており、飲食店のシェアが高いことも一つの特徴と言えるかも知れない。商業面では百貨店の売り上げ推移を見ると(丸井今井、三越、五番館、池内、カナリヤ)
1968年の売り上げ276億7400万円が1970年には370億円の売り上げとなり実に133.7%の伸びを示している。
1961年の北海道地区総広告費は106.2億円であつたが最終年度である1970年には310.1億円と2.92倍の伸びを見せた。叉、1965年は全国レベルと同じく総広告費で前年比98.6%となり、媒体別では新聞98.8%、ラジオ81.8%といずれも前年実績を割ったものの、テレビ広告費は前年比101.3%と辛うじて前年実績を確保する事が出来た。
図 19 北海道地区媒体別広告費推移
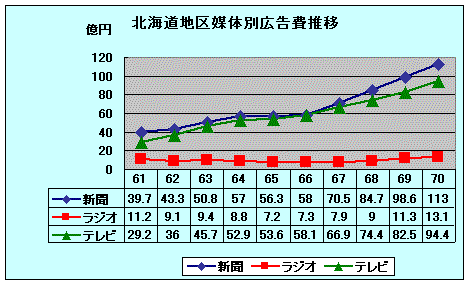 <北海道地区でのラジオの復権>
この間北海道では1962年12月15日第二局目のラジオ局としてSTVラジオが開局し、ラジオ二局体制となったものの1960年以降テレビに逆転された広告費の低落傾向に歯止めを掛ける事が出来なかった。しかし1965年以降これまでの低落傾向から反転してラジオも回復基調を歩み始めたのである。全国的ラジオ復権キャンペーン等の努力は北海道地区においてもHBC・STV両局の努力の結果、地区ラジオ広告投下額も1960代年終盤には過去最高値を示した1959年の12.9億円をクリアして13.1億円に達した。特に1968年から1970年にかけては北海道地区でのラジオの伸びはすざましく、テレビ広告費の伸びを凌駕する勢いを示したのである。
この好調の原因は3−4、3−5の項で述べたように北海道における自家用自動車普及(1965年から1970年5年間の伸び率は455.9%)を中心とする本格的モータリゼーション時代の到来によるカーラジオによる聴取人口の増加と、両局が競って地域に密着した番組づくりに努めた事が挙げられ様が、当時ラジオの特性として大きな反響を呼んだ放送の生・ワイド化が聴取者の身近なラジオとして更に拍車を掛け、地域広告主にラジオ広告を促す大きな力となったのである。そして1960年代終盤の1970年にはHBC・STVによるこれまでの聴取エリアの拡大と、両局の番組編成面での努力が実を結びこれらが広告費の面にも明るい局面を醸成し、これまでの低落傾向から反転して上昇機運に乗り1970年代の本格的なラジオメディア間の競合時代を迎える事となった。
< 新聞広告費に対峙するテレビ広告費>
一方テレビに関しては1968年11月北海道地区三局目の北海道テレビ放送HTBが開局し、これまでのHBC・STVの2局時代に終わりを告げたのである。
2局時代の最終年度である1967年の北海道地区テレビ広告費は66.9億円であったが、HTB開局後の1969年の同広告費は82.5億円と123.3%の伸びを見せ、メディアの増加によって着実にテレビ広告費が新聞・ラジオ広告ソースを浸食している実体が明確になったものの、投下額では未だ新聞に追いつくことの出来ないテレビ関係者にとっては切歯扼腕の年月を過ごす事となったのである。図19のグラフで見る様に北海道地区においては新聞・テレビ広告費が激烈なシェア争いを展開し、1965年の不況後翌年の'66年テレビ広告費が僅かにトツプに躍り出たが、その後叉新聞の巻き返しに遇い投下額に開きを生ずる結果となった。1965年は全国レベルで新聞広告費が前年比95.1%、ラジオ広告費94.7%といずれも前年実績割れとなり、テレビ広告費のみが102.7%と前年実績を確保した。同年北海道地区では新聞で98.8%、ラジオ81.8%と全国同様前年実績割れとなったが、テレビは辛うじて101.3%と前年実績をクリアした。しかし地区の総広告費は残念ながら前年割れという結果に終わったのである。この不況の一時期を除いては新聞・テレビは共に順調に広告費を伸ばし、新聞は1967年以降大幅な伸び率を示した。
電波広告費についてはラジオは1960年に前年実績を下回って以降1965年迄毎年広告費の低落傾向が続く苦難の道を歩み事となったが、前述の様に'66年以降局面が変わり上昇気流に乗ることが出来た。
一方、新聞広告費とテレビ広告費のシェアをメイン4媒体(新聞・雑誌・ラジオ・テレビ)で比較すると新聞広告費とテレビ広告費のシェアは全国レベルでは、1961年新聞広告費49.5%に対しテレビ32.4%その差17.1%、これが北海道地区では新聞46.4%に対しテレビ34.1%その差12.3%とテレビシェアが全国レベ
ルを上廻っていたが、1970年には全国レベルでは新聞広告費シェア45.3%、テレビ広告費シェア41.7%とその差が3.6%に接近した。しかしながらこの同時点での北海道では新聞シェア47.9%に対しテレビシェアは40.0%と全国レベルまでの追い上げには至らなかった。
北海道地区における総広告費に占める新聞広告費シェアは全国とほぼ拮抗しているが、中央(道外)対地元(道内)のシェアの比較では他府県と比較出来ないが北海道の場合地元広告費(道内)シェアの高さが他府県エリアに比べて高いのではなかろうかと推測している。この原因は北海道という広域エリアとしての地理的条件が大きな要因になっているのではなかろうか。かっての新聞は地域メディアとして地域住民に直結した情報源であり、日常生活に欠かせない活字媒体の持つ媒体特性が長い歴史の中で生活の一部として定着した結果であろう。
しかしラジオ・テレビと言う音声・映像メディアの出現によってこれまでの地域住民の情報収集の仕方にも大きな変化が生じ、新聞の持つ記録性に対しラジオ・テレビの持つ速報性、特にテレビの最大の武器である視覚に訴えるインパクトの強さは広告戦略では避けて通れないマーケッテイングツールとしてテレビ広告費の伸びに寄与する処が大きかった。とはいえ、企業広告を中心とした業種では活字媒体の持つ記録性と説得性に期待する広告主も多く、新聞特性に基づく広告出稿のあり方について我々としても充分研究すべきであろう。この観点から北海道における北海道新聞を中心とした新聞広告費の位置づけを真摯に評価しなければならないであろう。
新聞とテレビに関する調査資料として日本新聞協会が行った[2001年全国メディア接触調査報告書]がホームページ上で公開された。(http://www.pressnet.or.jp/adarc/chapter1/1-113.html)
これによるとテレビCMは[楽しい][印象に残る]といった感性に訴えるパワーが強いと指摘し、情報の種類によってメディアが使い分けされている実例を挙げ、一例として乗用車、携帯電話、食料・飲料などでは、[商品名、メーカー名、サービスの特徴、内容]等の情報収集はテレビが最大の情報源であることがアンケート結果から示されている。これらのテレビが持つ媒体特性を最大限生かしつつ新聞広告に対峙する事が必要であろう。
この項では1960年代の北海道地区広告費の中で地元広告費がどのような形で推移したかをメイン媒体を中心に検証し、特に新聞広告費の北海道での特性を検証する事としたい。
資料はいずれも電通の資料を参照させていただいた。
図20 北海道地区媒体別地元広告費シェア推移
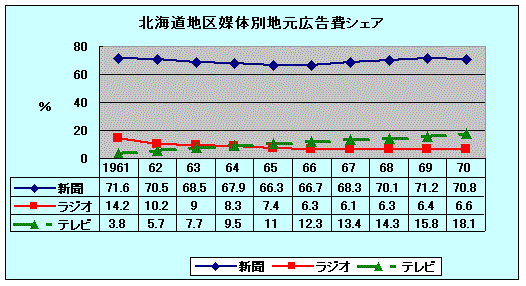 1960年代の北海道地区広告費(新聞・雑誌・ラジオ・テレビの4媒体)は10年間で150.4億円、約2.8倍の伸びを示したが、このうち地元広告費(北海道内投下額)は43.8億円で全伸び額の29%に留まり依然として道外からの投下額が大きい。この大きな要因はテレビ広告費に起因する。前述した様にテレビ広告はその多くを番組を中心としたネットワークに依存しておりテレビ広告費の10年間の伸び額65.2億円の78%に当たる50.9億円が道外広告主による出稿であり、地元出稿は14.3億円に留まっている。
一方地元広告費は1961年の26.8億円が1970年には70.6億円と伸び額で43.8億円約2.6倍の伸びを示したが、その伸び額の大半は札幌広告市場からの出稿によるものである。即ち札幌での広告費は1961年の17.4億円が1970年には51.5億円と10年間で34.1億の伸び額となり約3倍の伸び率を示した。このことを見ても1960年代の札幌が北海道の経済商業の中心都市として人口の増加に伴う消費マーケットとして拡大し広告市場としても大きく発展しつつある事が実証されるのである。
図20のグラフは地元投下広告費の媒体別シェアを示したものだが、地元広告費に関する限り新聞広告費のシェアはラジオ・テレビに比べても極めて高くこのシェアからも媒体の営業特性を窺い知ることが出来よう。
これまで見てきたように北海道地区での広告費の特徴の一つは、新聞広告費のシエアが全国に比べて大きく、電波広告費を凌駕している事が挙げられる。この事は地方ブロック紙として全国的にもトップランクにある北海道新聞、そして地域に密着した編集方針を堅持している地方紙に対する地域住民の信頼感、加えて地方広告主のメディアに対する高い評価、更には長い年月の間に培われた多角的な営業戦略等総合力の結果であろう。
ここでは先ず激烈なシェア争いを続ける新聞広告費とテレビ広告費との関係を見ることとする。北海道地区においては、1965年の不況を脱した新聞広告費が1967年以降着実にシェアを広げているのに対し、これまで順調な伸びを示してきたテレビ広告費が1968年、HTBの開局によりメディアの数が増えたにもかかわらず1966年をピークとして年々シェアがダウン傾向にある点が挙げられる。
図 21 北海道地区媒体別広告費シェア推移
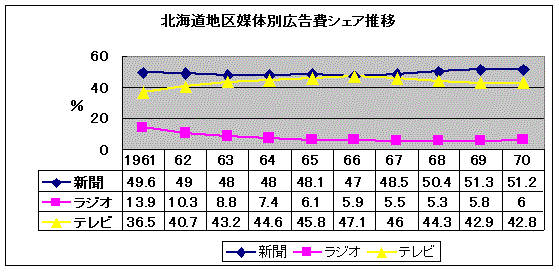 図21のグラフが示す様に、1966年僅少差でテレビに抜かれた新聞広告費が1967年以降拡大局面に転じるが、その要因を探る手だとして、次表の様に新聞広告費の道内よりの投下額を検証する事とした。 図 22 北海道地区新聞広告費地域別投下額
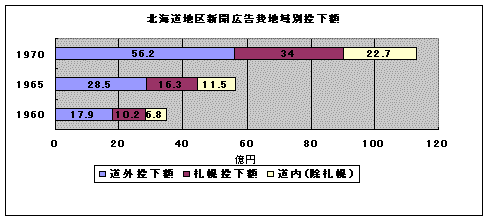 北海道地区での新聞広告費は1960年から1970年に至る10年間で78.0億円の増加となり伸び率は実に323.5%に達した。1965年は1960年に対し161.3%、これに対し1970年は1965年に対して200.5%と65年以降の伸びが極めて高いことが実証されている。
叉、この間の伸び額78.0億円の約50%が道内投下広告費の伸びであり、1970年が北海道における新聞広告費が道外投下額と道内投下額が拮抗し、(道外49.8%、道内50.2%)1971年以降年々道内投下額が道外投下額を上回る状況が生まれてくるが、このことは別項で述べる事とする。
さて、道内投下額の増加額39.7億円の60%に当たる23.8億円か札幌市場での伸び額であり、1970年前半の札幌オリンピック、これに関連する各種公共投資等、合わせて整備拡充が進む商業環境などの経済面での大きな変革が新聞広告の伸びに影響を与えたものと考えられる。北海道地区における新聞広告費の特徴は、1970年の地区広告費の中で、道内投下額が4媒体中70.8%を占めている。亦この60.0%が札幌市場よりの投下額であることが挙げられよう。
この事は北海道新聞社の社史 20年史・40年史等にも営業戦略の重点施策にローカル広告の再開発が採られたと記述されているが、それによれば北海道新聞広告収入が、1966年道内シェア49.1%に対し道外シェア50.9%が
翌67年には道内50.8%に対し道外49.2%と逆転し1979年には道内シェアは73.2%に達したのである。1970年時点での札幌市場での新聞広告費投下額シェアは、テレビ26.2%、ラジオ7.8%に対し実に66.0%のシェアを占めていた。
では札幌以外の道内各エリアの状況はどのような状況であるか、一言で言えば電波に対して新聞が圧倒的に強く同年時点での新聞広告費シェアは函館80.7%、旭川77.9%、釧路83.9%となっている。
|