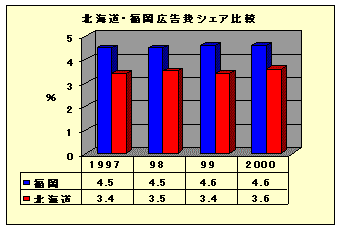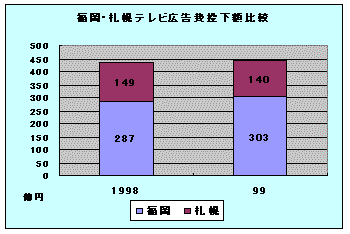��Z�́@�d�g�L���̕ϊv��
1989�N�[1999�N�@�@(�������N�[����11�N)�P�X�W�X�N1��7���ߑO6��33���V�c����̕����O���삯�߂��褎���͏��a���畽���ւƈڂ�ς��V������}�����̂ł���
�V�c����ɂ��N���������ɏ��a���畽���ւƕς������������ƊE�����̕�������̎n���_�Ƃ��ĐV��������ւƓ˓������
�@
���a����̏I�դ�P�X�W�V�N����n�܂����i�C�̏㏸�ǖʂͤ�ϋɓI�Ȑݔ������ɂ��ݔ��i�C�ɂ�袕����i�C��ƌĂ��V�����ǖʂݏo���A���̌i�C�͂P�X�X�O�N�܂ő��������������'�X�P�N�ɂ͉ߏ�ݔ������Ɗ�����n�����̖\���ƌ������Y���l�̌����ɂ��i�C�̋ǖʂ͈�]���Ģ�����s����ƌ������ދǖʂɒ��ʂ���������s���Ƃ����l�[�~���O�͋��s��w�{��`�ꖼ�_�����ɂ�����ꂽ���̂ł��邪������s���̈Ӗ��͢�����s���͓����̍s���߂��ɂ��s�������łȂ�����Y���z�̖\���Ƃ������Y�f�t�������s���ł��飂Ƥ�����͓����x�X�g�Z���[�ƂȂ�������������s����̒��ł����q�ׂ��Ă��顎��Y���l�̌����͐��Y����縷ݔ��������A���̌o�ςɑ���̉e����^�����̂ł���
�o�u�������̓��{�o�ς͂��̒Ɏ��w�����ċ��̓�����ގ��ƂȂ邪����̌�P�X�X�R�N�P�O�����Ƃ��Ĥ�P�X�X�U�N�ɂ͌���������Z��݂��i�C�����x�����钆�A�㔼�ɂ͐ݔ�������l����ɂ����邢���������܂�̕����Ɍ��������̂ł���
���̊ԂP�X�W�X�N�ɂ�3%�̏���ł��������ꂽ���A�P�X�X�V�N�ɂ͑��̗���5%�ɃA�b�v�����ȂǏ���҂̏�����ɂ��l�X�ȉe����^�����
�{��E��(��a�������ʌږ�)�͒���[���{�o�ϐ}���O��]�̒��ŁA���̕����s���������[���ł������̂͌����������I�Ńo�u���̕��傫�������Ă���Ǝw�E���A���̌����Ƃ��čɑ����ː��Y�}���ːݔ��������ނƂ����z�I�v������ɋ����A�����ĂP�X�X�R�N�̗�ĂƂ������R�����A���Y�f�t���ƌ�����l�ȃo�u���̕�����������Ă���B�����ĂP�X�X�O�N��̌i�C�ϓ������̎O�̊��Ԃɋ敪���Ă���B
�@ �P�X�X�R�N10����J�Ƃ���(91~93�N10��)���̌i�C���~���B
�A �P�X�X�V�N03�����R�Ƃ���(94~97�N03��)���̌i�C�㏸���B
�B �P�X�X�X�N04����J�Ƃ���(�X�V~�X�X�N)���̌i�C���~���B
�i�C���P�X�X�T�N�ȍ~�㏸�@�^������ꂽ�����̔N��1��7������������_��W�H��k�Ђ͎Y�Ǝ{�݂͂��Ƃ��Z���̃��C�t���C���������S�ɕ���Ȃlj�œI�ȃ_���[�W��^�����������3���ȍ~�̋}���ȉ~�����������������n���S�𒆐S�ɂ��ċN�������T���������Ƃ����c�E�ȍs�ׂȂǤ�����Ɍo�ϖʂ݂̂Ȃ炸�Љ���̖ʂł��Â��e�𓊂��������̂ł��顂��̂��ߌi�C�̉�ɂ������ݏ�Ԃ�����ꂽ��o�u������̏��Ղ͐[���A�P�X�X�U�N�͂��̏����������ďZ���肪�傫���N���[�Y�A�b�v�������Ɗ֘A���ċ�s�̎Љ�I�ӔC�����ꂽ1�N�ł�������P�X�X�V�N�̓}�N���o�ςƂ��Ă͌i�C�̉͒����ɐi�s���ɂ₩�ȉ�ɂ���ƌ����Ă������̂́A����ŃA�b�v�A��Ô�̉���Ȃnjl�̉��������̌������炭�����}�C���h�̒ᗎ�A�ݔ������̗������݂Ȃǂ̉e������i���͌������ɒ��ʂ��A�ꕔ�ɂ́u�����s���v�ƌ�����i�C�̑����ݏ�ԂɏI�n�����B
�@
�����N��ɓ���A�q�������铮���͍Q���������A�P�X�W�X�N�R���U���ɂ�JC-�[SAT(���{�ʐM�q��)�A�T���P�R���ɂ�SCC(�F���ʐM)���ł��グ���A�ʐM�q�����g�p����ԑg������ЁASNG�A�r�W�l�X�e���r�APCM�������̌v�悪������̉��������A����[�q�����N����]�ƌĂԂɑ��������ƊE���ɂ������B
�P�X�X�O�N��̂P�O�N�Ԃ͂Q�P���I�̖{�i�I�����q���E�����f�W�^�����Ɍ������������ԂƂ��ėl�X�ȓ�������������A�{�i�I�ȉq����������̏������Ƃ��Ĉʒu�Â����悤�B�P�O�N�Ԃ̓����̒������v�Ȃ��̂����n��I�Ɍ���ƁA�䂪���A���ԕ����q���̖{�i�I�ȃX�^�[�g���_�ƂȂ����͉̂q���f�W�^�������R�Ђ̐ݗ��ł��낤�B����NHK(1989.6��)�A���{�q������(WOWOW1991.4��)�͖{�������J�n���Ă������A�f�W�^�������R�Ђ̐ݗ����f�W�^�������̋@�^���ꋓ�ɐ���グ��]�@�ƂȂ��B
�P�X�X�S�N�P�P���P�O���ɂ͓��{�f�W�^�������T�[�r�X(�p�[�t�F�NTV)�A�P�X�X�T�N�X���Q�W���ɂ̓f�C���N�E�e�B�r�[(�f�C���NTV)�A�X�ɂP�X�X�U�N�P�Q���P�U���ɂ̓W�F�C�E�X�J�C�E�r�[(J�X�J�CB)���������Őݗ�����A�P�X�X�U�N�P�O���̃p�[�t�F�NTV�̕����J�n����ɁA�f�C���NTV���P�X�X�V�N�P�Q���������J�n�����B��Ăɗ����オ����CS�f�W�^���������P�X�X�W�N�T���ɂ͓��{�f�W�^�������T�[�r�X(�p�[�t�F�NTV)�ƁA�W�F�C�E�X�J�C�E�r�[(J�X�J�CB)���Γ��������A�T�[�r�X����[�X�J�C�p�[�t�F�NTV]�ɕύX�������A���̌�Q�O�O�O�N�ɓ���R���Q���A���{�f�W�^���T�[�r�X(�X�J�C�p�[�t�F�NTV)�ƃf�C���N�E�e�B�r�[(�f�C���NTV)��CS�������Ƃ̓����𐳎��Ɍ��肵�A�Q�O�O�O�N���������ăf�C���NTV�̃T�[�r�X�͑ł�����ꂽ�B����ɂ����{��CS�������Ƃ͒a������O�N��[�X�J�C�p�[�t�F�NTV]1�ЂɏW��鎖�ƂȂ����B���A�j���[���f�B�A�̈�ł���CATV�ɂ��Ă��d�C�ʐM�R�c��͂P�X�X�X�N�T���R�P���S����CATV�𐼗�Q�O�P�O�N�܂łɃf�W�^�������鎖���]�܂����Ƃ̓��\���s���A�Q�P���I�Q�O�P�O�N�Ɍ�����CS�����ABS�����A�n��g�����ACATV�̃f�W�^�����v�悪��������鏈�ƂȂ��BCATV�Ɋւ��Ă̓R���T���^���g���[�V�[�h�E�v�����j���O]���Q�O�O�W�N�܂ł̃P�[�u���e���r�̎s��\����Z�ߔ��\���Ă���B���̕��ɂ��P�X�X�X�N�R�����݂�794�����тɕ��y���Ă���P�[�u���s��͂Q�O�O�W�N�܂łɂ͂Q�W�O�O�����т܂Ő�������Əq�ׂĂ���B���A�Q�O�O�W�N�̃P�[�u���s��̕����T�[�r�X�̔���グ�͂U�O�O�O���~�Ɛ��肷��ȂǁA�����̃P�[�u���s����n��g�e���r�ɂƂĂ͋����}�̂Ƃ��Ē��Ӑ[�������K�v�����낤�B����Q�O�O�O���ɂ�BS�f�W�^���������J�n���ꂽ���A���̎���́A������ǂ����ꂼ��̌n��e�ǁA�֘A�O���[�v�A�ًƎ��Ƃ̎Q��̂��ƐV��Ђ�ݗ�����ȂǕ����̐��̐������i�߂�ꂽ�B
�P�X�W�X�N�̓��{�̍L�����50.715���~�ł���������P�X�X�X�N�ɂ͑��̊z��56.996���~�ƂȂ�P�X�W�X�N��100�Ƃ���P�X�X�X�N��112.4%�ƈꌩ�����Ȑ����H��������Ɍ����邪����̊ԓ��{�o�ς͕����i�C�̔�������o�u������ƌ����o�ς̍�����h�邪���悤�ȑ�n�k�ϓ����ɒ��ʂ����B�L����̖ʂł������̌i�C�f���ĂP�X�X�Q�N��X�R�N�͓�N�A���̑O�N���ъ��ꤑ����P�X�X�S�N���O�N���є�100.8%�Ƃ����ɂ߂Č������L�ї��ɗ��܂�����K���P�X�X�T�N�E�X�U�N�͐L�ї�������ȏɖ߂������̂̂P�X�X�W�N�E�X�X�N�͍Ăь������ǖʂ��}���錋�ʂƂȂ����B
�}�@45�@�S���}�̕ʍL�����
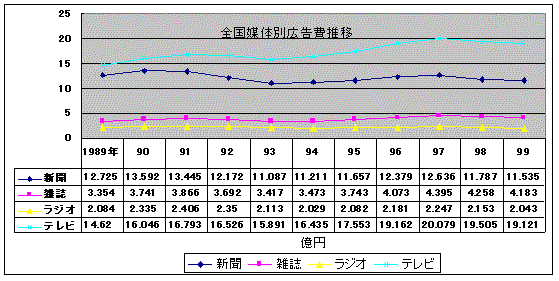 ��̕\�������l�ɂP�X�X�Q�N�E'�X�R�N�͐V����G������W�I��e���r���}�X�R�~4�}�̂͑S�đO�N���ъ���ƂȂ褏]���đ��L��������̗��N�͑O�N����Ƃ������������Ő��ڂ�����K���i�C�̉ɔ����P�X�X�S�N�ȍ~�V����G����e���r�͑O�N���N���A�����Ƃ͌������̂̑O�N���т�h�����Ċm�ۂł����Ԃł��褃��W�I�͓��N�����������O�N���ъ���ƂȂ�R�N�A���̑O�N���ъ�����L�^�������̃O���t�ɂ͕\�L���Ă��Ȃ����A���L����͂P�X�X�Q�E'�X�R�N�̕s�U����E���P�X�X�S�N�ȍ~�����ɐ��ڂ��P�X�X�V�N�͉ߋ��ō��z��59.961(���~)���L�^�������A���N�ɓ��荑���i�C��ދǖʂ̉e������57.711(���~)�ƑO�N���т�����A�����ĂP�X�X�X�N��56.996(���~)�ƍĂёO�N���т�����錋�ʂɏI������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �}�@46 �S���L����}�̕ʃV�F�A
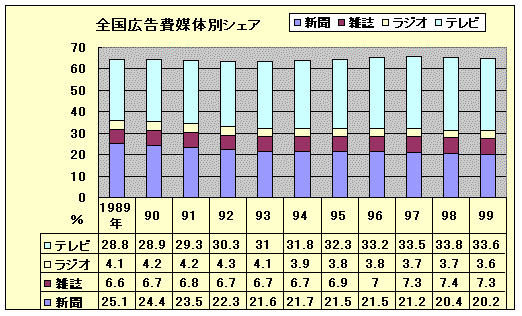 �@ �@�}�X�R�~4�}�̂̑���SP�L���弄j���[���f�B�A�L�����������100�ƂȂ�
�@
��̃O���t�Ō���悤�Ɏ���̗���Ƌ��ɔ}�̕ʃV�G�A�͑傫���ς����顐U��Ԃ��ēd�ʒ������X�^�[�g�����P�X�S�V�N�͓d�g�L����͑��݂����V����G����r�o�L����݂̂œ����̃V�G�A�͐V��75.4%��G��10.9%��r�o13.7%�ƋL�^����Ă��顉䂪���ɍŏ��̖������W�I�ǂ��J�ǂ����P�X�T�P�N�ɏ��߂ă��W�I�L����v�コ��͂���1.2%�̃V�G�A���m�ۂ��Ă���
���̌ド�W�I�ǂ̑������J�Ǥ�����ĂP�X�T�R�N����̃e���r�NJJ�ǂɔ����e���r�L����̌v��ȂǓd�g���f�B�A�̐�������W���ɕς��Ȃ��L�����ێ����Ă���SP�L���賈^�[�Q�b�g�ʂɉv�X�ו�������N�X�L���V�F�A���g�傷��G���L���洛���������}���L���r�W�l�X�Ƃ��Ă��r���𗁂т���C���^�[�l�b�g�֘A�L�����܂߂��j���[���f�B�A�L�����L����̗��������̌o�ϥ�Љ���Ƌ��ɕς����邪��L����T�O�N�̗�����T������A�V���L����͂P�X�S�W�N�S�L����ɑ���V�F�A��84.9%���ō��ɍ����܂Ŋ���̒i�K���o�Ă�����P�X�U�O�N�ɂ͂���܂Œ����ԕێ����Ă���70%-50%��̃V�F�A��30%��ɗ������ނ̂ł��顂P�X�T�X�N�̍c���q���������̃e���r�L����̋}���ȐL�тɂ��Ă͊��ɏq�ׂ������N�̃e���r�L���16.4%�ƑO�N��6.5%�̃V�G�A�A�b�v�ɑ���V���͓��N42.5%�ƑO�N��6.8%�̃V�G�A�_�E���ƂȂ褗��N39.3%�ƂȂ��̂ł��顂����Ă��̌�N�X�V�G�A�𗎂Ƃ��Ȃ���30%���ێ����Ă������A�P�X�W�S�N�V�G�A��30%�������29.0%�ƂȂ�������a�̏I�Ղ���20%����J��Ԃ��Ȃ��猻��20%�䂬�肬��̃V�G�A�ƂȂ��Ă��顈���e���r�̍L����V�G�A�͂P�X�T�X�N����̓]�@�Ƃ��Ă��̌�N�X�V�F�A���g�債�P�X�U�R�N�ɂ�30.1%�ɒB���A���̌㈽�����V�F�A�_�E���𗈂������̂̌��݂܂ŊT��30%���ێ����Ă�����P�X�V�T�N�ɂ͑O�q�̂悤�Ƀe���r�L����V���L����𗽉킵�]���ăV�F�A�̖ʂł��e���r���g�c�v�̍����ˎ~�߂鎖�ƂȂ����̂ł��顂�������̃O���t�̓}�X�R�~4�}�̂̃V�G�A�̐��ڂł��褂���ɂ͋L�ڂ��Ă��Ȃ����L����̒��ŏ�Ɉ��̍L�����ێ����Ă���̂�SP�L����ł��顂P�X�X�X�N�ł̓}�X�R�~4�}�̂̃V�G�A��64.7%�ł���̂ɑ��SP�L����V�G�A��34.5%�ł��顔̔��ɒ��������L����̌����I�^�p����ʃ`�����l���h���Ə���҂̍w�����@���h������DM��`���V��܂荞�ݥPOP�������̍L����̑��݂����邱�Ƃ͏o���Ȃ�������ɑR����d�g�}�̂̉c�ƊJ��������đ����f�B�A�ƘA���������f�B�A�~�c�N�X������̌����͍X�ɕK�v�ƂȂ�ł��낤�
�X�ɍ���̓����ɑ傫�ȊS�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂̓j���[���f�C�A�L����ł��顂���܂œd�ʂ̍L����ł�CATV�E�q�������Ȃǂɓ������ꂽ�L������j���[���f�B�A�L����Ƃ��Čv�サ�Ă������A�}���ɐ����𑱂���C���^�[�l�b�g�L���ɑΉ����ׂ��P�X�X�X�N���͒P�Ƃ̃A�C�e���Ƃ��Čv�シ�鎖�ƂȂ����B�Q�O�O�O�N�̉q�����f�B�A�֘A�L���E�C���^�[�l�b�g�L�����856���~�O�N��183.7%�Ƌɂ߂č����L�т��������B�d�ʂł͂Q�O�O�O�N2������̍L����̗\���Ƃ��ĂQ�O�O�S�N�ɂ�1000���~�A�Q�O�O�V�N�ɂ�2000���~�ƁA���W�I�L���Ɍ�����ׂ邾�낤�Ƃ̕��s���Ă��邪�A�e���r�E�V���E�G���E���W�I�Ɏ�����܂̍L���}�̂̈ʒu���߂���̂������ł���B����A���o�ό�������[�C���^�[�l�b�g�L���s�����2000]�̕��ł̓C���^�[�l�b�g���p�l���̋}����w�i�Ƀl�b�g�L���s��͂Q�O�O�S�N��1510���~�[2300���~�ōL�����3%�O��̃V�F�A�ɂȂ�Ƃ̗\�����o���Ă���B����S�����x���ł͋}�������f�B�A�Ƃ��Ē��Ӑ[�������K�v�����낤�B
����܂ł͕����ɓ����Ĉȍ~�̍L����ɂ��ēd�ʎ������Q�l�ɔ}�̕ʓ����z�̐��ڤ�V�G�A�̊W�������Ă���������ɍL����̒n��I�����z���N��Ƌ��ɂǂ̂悤�ɕς����邩�����鎖�Ƃ�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
5-2��e���r�L����̎���I�ω���̍��ŏq�ׂ��l�ɑ�s�s�W������X�|�b�g�d���̓����͔N�X�傫�ȗ���Ƃ��Ē蒅����X���ɂ��鎖�𓌋����㥖��É���k�C��(�D�y)��4�n��̃X�|�b�g�����V�F�A(�P�X�W�T�N-�W�W�N)�Ŕ�r�������A���̍��ł̓}�X�R�~4�}�̂̒n��ʓ����z��e���r�L���弄��W�I�L����e����̃V�G�A��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�} 47�@�S���L����C���S�}�̒n��ʓ����z�V�F�A
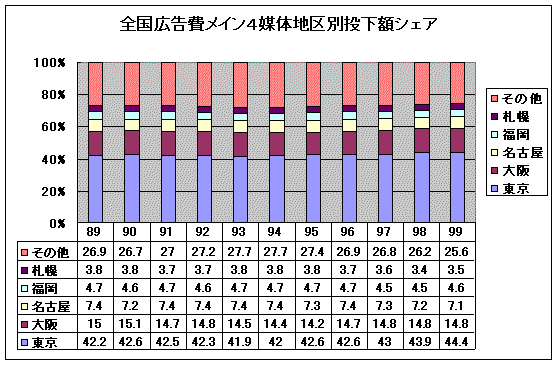 ��̃O���t�ͤ�}�X�R�~4�}��(�V����G������W�I��e���r)�̕����N�x�̊e�n�擊���V�F�A�̐��ڂł��邪��e�n��̓����V�G�A���N�x�ɂ���̕ϓ��͂�����̂̑����ČŒ肵���������顃��C���S�}��(�V����G������W�I��e���r)�̖k�C���n��V�G�A�Ɋւ��ďq�ׂ�Τ�k�C�����P�X�T�O�N���5%��̃V�F�A��ێ����Ă������P�X�U�O�N��ɂ�4%��ɗ������B�����ĕ����̌��݂͐���3%��ɒᗎ�������̃V�G�A�_�E�����뜜�����ł��顉ߋ��k�C���͕����n��ɑ��L����̖ʂł��D�ʂȗ���ɂ��������N�X���̍����k�܂茻�݂͖k�C����1%���̃}�C�i�X�ƂȂ��Ă��顓���A�W�A������������B�n��̌o�ϔ��W�Ɩk�C���̌o�ϓI��������ʂƌ����ׂ�����o�ςƍL����̑��֊W�������Ă��銴����������̂ł���
�}�@48�@�S���e���r�L����n��ʓ����z�V�F�A����
�@
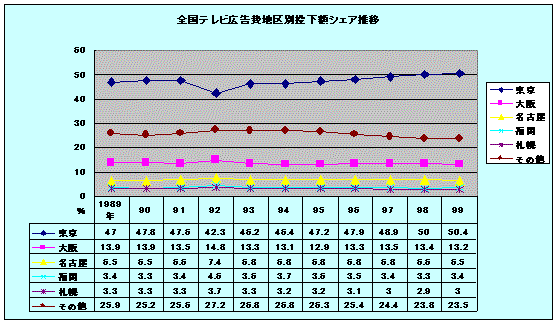 �N�X�L����̌����I�^�p���w������i�V���i���N���C�A���g�̐�`���j�f���đ�s�s�W�����̌X���������ɂȂ����B���̖ʂ�����n���L����̃V�F�A�A�b�v������̒n���ǂ̑傫�ȉۑ�ƂȂ낤�B
�}�@49 �S�����W�I�L����n��ʓ����z�V�F�A���� 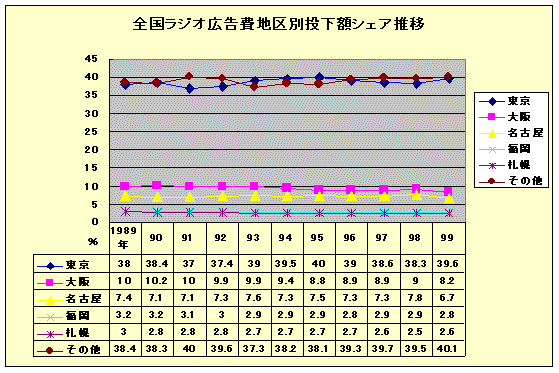 ���Ƀ��W�I�ɂ��Ă��̒n��ʓ����z���ǂ̂悤�Ȑ��ڂ�H���Ă��邩�������Ă݂����
�O�f�O���t�̃e���r�L����e�n�擊���z�V�F�A�ƁA���W�I�L����e�n�擊���z�V�F�A���r���ė��҂̑���_�̓e���r�ƃ��W�I�L����̎��I�ȈႢ���琶���Ă���
�e���r�L����͔N�X��s�s�W�����̌X�������ߒ����W��I�F�ʂ��Z���Ȃ����̂ɑ�����W�I�L����͔}�̓��������ꂼ��̒n��ɖ����������[�J�����f�B�A�Ƃ��Ă̋@�\���������߁A�L���ʂł����������^���͒n��W��^�ƌ������F�������Z������Ƀo�u������㒆���L����̃��W�I�L���\�Z�̍팸�X���ɔ������W�I�̃l�b�g���[�N�ɂ��X�|���T�[�l�b�g����ނ���������L�[�ǂƂ����ǂ��S���l�b�g���͊֓����[�J���G���A�̉c�Ƒ�ɏd�_��u�����L�����y�[���W�J��}��ȂǑ�����ɕ��S����X�����o�n�߂��פ�n�����W�I�ǂ͒����ˑ��^����n��ɓO�����Ǝ��̔ԑg�J���Ɖc�Ɛ헪�ɑS�͂𒍂����ƂȂ�A���̌��ʂ��e���r�ɔ�r���ă��W�I�L�������̒n���V�F�A�����߂�傫�ȗv���ƂȂ����Ɨ������ׂ��ł��낤�
�@
�P�X�W�O�N��̏I�դ���ň��ƌ���ꂽ�k�C���̌o�ϊ����A���̌�P�X�W�W�N�ȍ~�i�C�̉ɂ��㏸���[�h�̒��ɕ����V������}��������̈Ӗ��ł͂P�X�W�X�N�͖k�C���o�ςɂƂ��Ă͌i�C��3�N�ڂɓ����蕽������͏����ȑD�o�ƂȂ����̂ł���
�P�X�W�W�N�͑O�q�̂悤�Ɍ������Ƥ�Z��ݤ�l����ɂ߂č��������Ő��ڂ��A���̏��P�X�X�O�N��ɓ����Ă����̂܂������D�����������Ă�������P�X�X�Q�N�ȍ~�͑S���̌o�ς̗���Ɠ������i�C�ɂ��A�肪�����������X�������݉����A�S�̂Ƃ��Ē���C���ɐ��ڂ�������ɂ��̎����k�C���o�ςɂƂ��Ă̏ے��I�ȏo�����͂P�X�X�V�N�P�P���P�V���̑��̔j�]�ł������B����܂ʼn䂪�����Z�E�̃r�b�O�o���ƌ����傫�ȗ���̒��ŁA�{���ɂ����Ă��ꎞ�����Ɠ���̍������捹������Ă����o�܂������������ɁA�ˑR�̃j���[�X�͓����ɑ�ςȏՌ���^�����B����P�X�O�O�N�ݗ����ꎢ���{���J���̕��݂Ƌ��ɏ�ɖ{���̌o�ϊE�E�Y�ƊE�̃��[�h���Ƃ��Ē����I�Ȗ������ʂ����ė����k�C����B��s�̔j�]�͖k�C���o�ςɌv��m��Ȃ��e�����y�ڂ����ƂȂ����B���̔j�]�ɂ��c�ƌ��͖k�m��s�ɏ��n���ꂻ�̌�~���ɋ��Z�V�X�e�����쓮���Ă�����̂́A�j�]�ɂ�蒼�ځA�Ԑڂɉe���������l�X�ȕ���ł̏��������݂����s���ł���o�u���̏��Ղ̑傫�����������߂Ă���̂�����ł��낤�B���̔j�]�����Ėk�m�ւ̉c�Ə��n���{�����Z�ĕҐ��̑�ꖋ���Ƃ���A��͖k�m�E�D��(�D�y��s)�̎�������Ђɂ��S�ʒ�g�ł��낤�B����̐����c����������T�o�C�o���헪�̈�Ƃ��ė��Ђ̋�����������Ђł���[�D�y�k�m�z�[���f�C���O�X](�В��@���������@�k�m��s����)���Q�O�O�P�N�S���Q�����������Ђ̌o�c������^�тƂȂ����B�X�ɍĕҐ��̑�O���͓����e�n��̐M�p���ɁE�M�p�g���̍��]�A�t�ł���A���ɂ��̍����������e���œW�J�������B
�d�g�L���������o�ϊ��Ƃ͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���A���݂̍L����̗�����������ł������N�㏉�����獡���Ɏ���k�C���E�D�y�o�ϊ����ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă��������͂��邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�ł���B���̈�Ƃ��Ă��̔N��̎����o�ϐ�������k�C���E�S���ƑΔ䂵�ĉ��L�ɃO���t�������B
�}�@50�@�����o�ϐ������̐���
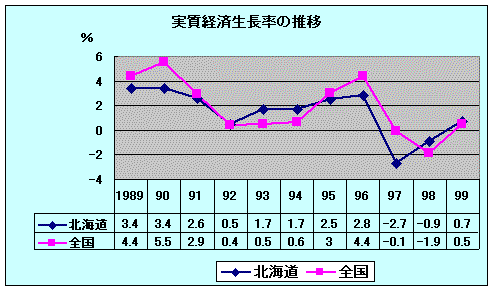 �@
��̃O���t�������l�ɂP�X�X�Q�N�ȍ~�S���E�k�C�����Ƀo�u������̒Ɏ���Ď������������ɂ߂Ēᗦ�Ő��ڂ����
���̈Ӗ����猾���Ζk�C���o�ς͂P�X�X�Q�N�s���̂ǂ��ɚb�����ƌ����悤�B����ȍ~�k�C���̐������x�������������ό����i�C�̌����͂ƂȂ��đS�����ς��͍�����������ێ����邱�Ƃ��o��������̌�i�C�͏㏸�ǖʂɓ]�������̂̂P�X�X�V�N�ɂ͍ĂёS���I�Ȍi�C��ނɂ��A�S���E�k�C�����Ƀ}�C�i�X�����ƂȂ����B�k�C���̉ߋ��̐����������Ă��P�X�W�O�N�[�P�X�W�T�N�͗�Q�ɔ����e�����ĂW�P�N�E�W�R�N�ɂ̓}�C�i�X�������L�^�������A�P�X�W�T�N�㔼�����Ă���͈�]���č������ɓ]���鎖�ƂȂ����B���̌�P�X�X�O�N��ɓ���ɂ₩�Ȑ������������Ă������A�P�X�X�Q�N�ɂ̓}�C�i�X0.5%�A�P�X�X�V�N�ɂ̓}�C�i�X2.7%
���L�^�����B
�@
�}�@51�@�D�y�s�̌o�ϐ������E�s�����x�o�L�ї� 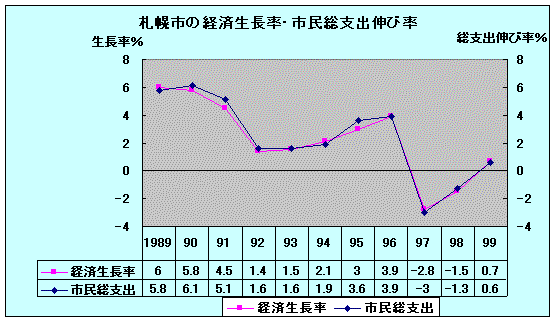 ��̃O���t�͎D�y�s�̎����o�ϐ������Ǝs�����x�o�̑O�N�L�ї������������̂����A�P�X�X�Q�N�ȍ~����������~����H��ꎞ���_�@�̉������ꂽ���̂̂P�X�X�V�N�A�X�W�N�̓}�C�i�X�������L�^���鎖�ƂȂ����B ����Z��֘A�ł͐V�K�����H�������A�P�X�X�P�N�A'�X�Q�N�X�ɂ�'�X�V�C'�X�W�C'�X�X�N�ƌ������Ă��邪�A�����̎w�W������i�C�̉A�茻�ۂ��M���m�鎖���o����̂ł���
�}�@52 �D�y�s�̌o�ώw�W
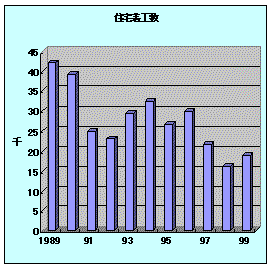 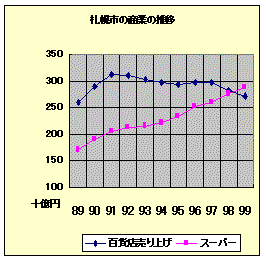 ��̃O���t�Ō���ʂ�A���̓��̈�ł���S�ݓX�̔��z�ɂ��Č����ΎD�y�s�̏��Ɠ��v�ɂ��S�ݓX�̔��z�͂P�X�X�Q�N�ȍ~�N�X�����X���������A�����ăX�[�p�[�̔���グ���N�X�����X���ɂ���B���̌��ۂ͏���҂̍w���s���̕ω��Ƒ�^�X�̗��n�����ȂǐV�����s�s��������ɂ��Ă���B
���̌X���̓O���t�ɂ͕\���Ă��Ȃ����S���e�n��Ɍ����錻�ۂł���B
���݂ɂP�X�X�X�N�̏��Ɠ��v�����ɂ�铹���̑�^�����X���͂P�P�V�S�X�ƁA�����A���A���m�A��ʂɎ����őS���ܔԖڂƂȂ��Ă���A�O��P�X�X�V�N�̒������ɔ�ׂĂ�6.1%�̑����ƂȂ��Ă���B���̒��ł��ŋ߂͓����l���P�O���l�K�͂̒n���s�s�ւ̏o�X���ƁA�D�y�s�̐V���Z��n�ւ̏o�X���ڗ����Ă���B���̗l�ɃX�[�p�[�X�̔��グ�������������ăX�[�p�[�A�R���r�j�X����v�s�s�x�O�^�X�܂Ƃ��đ������Ă���w�i�ɂ͖{���̒n�搫�Ƃ��W���Ă���A�J�[�V���c�s���O�̑����ɔ������ԏ�X�y�[�X�̊m�ہA�������̗��n����������ɔ��Ԃ������Ă���Ƃ������悤�B���������Ӗ��ł͖k�C���Ƃ����L�挗�ł̃}�[�P�b�e�C���O�����ɂ͑S���ɘi��X�[�p�[�E�Z���t�X�ւ̗��ʃA�v���[�`���ɂ߂ďd�v�ł��鎖�������o���悤�
�l���̑����ƕ����ĎD�y�s�̑傫�ȕω��̈�͎Y�ƍ\���̕ω��ł���
3-3��P�X�U�O�N��̖k�C����D�y�s�̌o�ϓ�����̒��ŎQ�l�����Ƃ��ĂP�X�U�O�N�'�U�T�N�'�V�O�N�̎Y�ƍ\���ɐG�ꂽ����P�X�V�O�N���_�ɂ�����D�y�s�̑�O���Y�Ƃ̃E�G�C�g
�͑S�A�ƎҐ���72.7%�ƍ�������ɃT�[�r�X�Y�Ƃ��傫���������Ă��邱�Ƃ��w�E���������̌�̗���������f�[�^�[�Ƃ��ĂP�X�X�P�N�E�P�X�X�U�N���{�̑���������Ə�������ƎD�y�s�̢�o�όv�Z�N����Q�l�ɋL�ڂ���
�@
�@
(�Q�l)�@ �Y�ƕʎ��Ə���A�ƎҐ����z�@�@�@ �P�ʁ@�@��
�@
��\�̗l�ɂP�X�X�P�N��'�X�U�N�̎Y�ƍ\���䗦�͊T�˓����ł���A�O�q�̗l�ɑ�Y�Ƃ��S���ɔ�r���ď��Ȃ��A��O���Y�Ƃ̔䗦���傫�����Ƃ��k�C���E�D�y�s�̎Y�ƍ\���̓����ł���B�D�y�s�̏ꍇ��O���Y�Ƃ̒��ł������傫�����ނ���Ƣ�������������H�X��̃E�G�C�g������43.3%���ߤ�����Ţ�T�[�r�X�ƣ��25.6%�ƁA���̓�Ǝ킪��O���Y�Ƃ̑傫�ȃV�F�A���߂Ă���B
����P�X�X�X�N�Ɏ��{������H�Ɠ��v������Ō���Ƒ�O���Y�Ƃ̕���ł̍ŋ߂̌X���Ƃ��ďo�ť����Ƃ���Ɋ֘A����Y�Ƃ��L�тĂ��褂��̃V�G�A�ł͎D�y���������Ƃ��ڗ����Ă��顈��݂ɃV�F�A�W�ł͎D�y�̎��Ə�����391�ŁA�S����862�ɑ���45%�A�]�ƈ����ł��S����55%�ƁA�D�y�ɏW�����Ă��邱�Ƃ������Ă��顎G���L����̐L�тɊ֘A���ĂP�X�V�O�N��̎D�y�s�ɂ�����s��̓����ɂ��Ă�4-5��k�C����v�G���A�ʍL���ŋL�q��������L����̐L�������̂悤�ȎY�Ɠ��Ԃ̕ω�����M���m�鎖���o����̂ł���
�{���̌i�C�̌����͂Ƃ��đ傫�Ȃ��̂͌������ƂƊό��ł��邱�Ƃ͊��ɒm����ʂ�ł��邪�A�ό��Ɋ֘A���ĎD�y�s�̊ό����C�x���g�Ƃ��ċr���𗁂тĂ���̂��P��̓~�̐�܂�ƁAYOSAKOI�\�[�����܂�ł���B����ɉĂ̕������Ƃ��Ē蒅������ʃr�A�K�[�f����������Ċό����ʂƋ��Ɍo�ό��ʂ��傫���]���������B�@�D�y�s�ό������ׂ̎��т��Q�l�����Ƃ��ăO���t�ŕ\������B
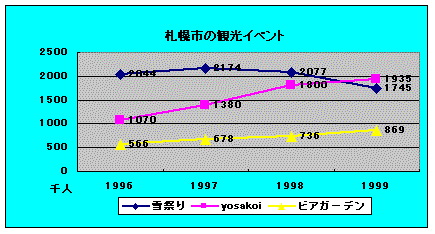 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�͂łP�X�W�O�N��I�Ղ���P�X�X�O�N��ɘj��k�C����D�y�s�̌o�ϊ��ɂ��Ă��̊T�v���q�ׂ�������̊ԍL����͂ǂ̂悤�Ȑ��ڂ�H���č������}���Ă��邩�������Č������
�P�X�W�X�N�̃��C���S�}�̂̍L����ͤ�O�N�ɑ��L�ї�128.7���̑��ƂȂ�������̒��ł��V���̐L�ъz���O�N��162.4%�ƐL�ъz���̂�80.5%���߂Ă��顂P�X�W�X�N�̃��C���S�}�̂̐L�ї���128.7%�ƌ��������L�ї����グ�Ă���̂���ɂ������ĐV���̐L���ɂ����̂ł���
��X�ɂƂ��ĐV���L������̔N�ɂ߂č����L�т��������͉̂��ɋN������̂��͋ɂ߂ċ����̂��鏈�ł��邪����͎��̂悤�Ȏw�W������n���o�ς̍D�����V���L����Ƀ_�C���N�g�ɗǍD�ȉe�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��顑����P�X�W�X�N�̖k�C���o�ς͂P�X�W�T�N����̌i�C�̉�����̂܂��������ڂ�����D�y�𒆐S�Ƃ���S���Ɣ�r���Ă̍����������ƕ����ē��Ɍ����ȓ_�͖��Ԑݔ��������O�N�x��9.9%�㏸������̈��Ƃ̊g��ɔ����J���͂̊m�ۂ��e��ƂɂƂ��Ă��傫�ȉۑ�ƂȂ�J���͂̎��v�x���}���ɍ��܂����פ�V�K���l�����O�N��19.4%��L�����l�{����0.61�ƁA�P�X�V�S�N�ȗ��̍������ɒB�����̂ł��額X�ɐV���L���Ƃ��đ傫�ȍL���\�[�X�ł���Z��ݤ���ł������Z��(�����}���V�������܂�)�̌��݂͂P�X�U�U�N�[�P�X�V�O�N�̢�����Ȃ��i�C��ȗ��ƌ����A����炪�傫���V���L���̏o�e���Ɋ�^�����Ɨ������Ă��顂����������i�C����o�u���̕���͍L����̖ʂɂ��傫�ȏ��Ղ��c������P�X�X�Q�N�����X�R�N�̘A���Q�N�ɘi��e�}�̂̑O�N���ъ���͊e�ƊE�W�҂ɒɗ�ȃ_���[�W��^������K���P�X�X�S�N�ȍ~�̒��������������̂̍D�i�C�͒����������P�X�X�V�N�ȍ~�Ăь������ǖʂɑ��������B���ɂP�X�X�W�N�̓��C���S�}�̂���������O�N���т��N���A�o�����A�����P�X�X�X�N���G���E�e���r���h�����đO�N���т��N���A�������̂�4�}�̂̑��v�ł͑O�N����̌��ʂƂȂ����B���̂悤�ȍL����̗��������ɂ��L�ї��͂����Ă�2�������ɂ͒���������悢�摽���f�C�A����ɂ�����ᐬ������̓�����������������̂ł���
�d�g�}�̂̐��ڂɂ��Ă͕ʓr���͂��s����������ɓ����ĐV���ƃe���r�̊W�͍Ăу}�X�R�~�S�}�̂̃g�b�v�̍���V�����D�A�ȍ~���̍����ێ����ė������A�N�X�i���͏k���̌X���������A�P�X�X�W�N�Ɏ���Җ]�v�����e���r�L����V���L����𗽉킷�鎖���o�����B�K����������'�X�X�N�A'�O�O�N���������錋�ʂƂȂ������A����X�Ȃ�w�͂ɂ�肱�̗�����������鎖���e���r�c�Ɗ����ɉۂ���ꂽ�傫�ȉۑ�ł��낤�B�i���̃O���t�Q�Ɓj
�}�@53�@�k�C���n�惁�C���S�}�̍L�������z����
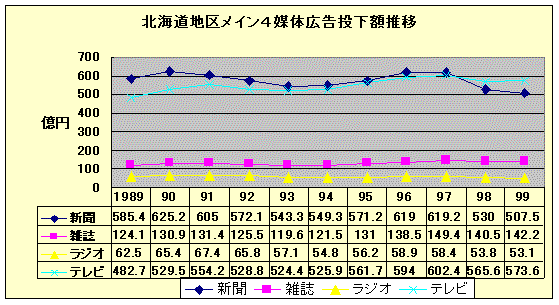 ���̌��ʎ�v�R�}�̂̃V�F�A�͂ǂ̂悤�ɕω��������𓊉��z�V�G�A�̐��ڂŌ��邱�ƂƂ��顁@ �@�}�@54 �k�C���n�惁�C���R�}�̍L����V�F�A����
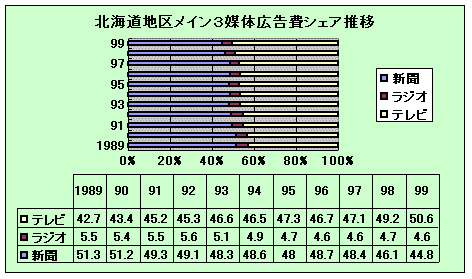 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�q�̗l�ɖk�C���n��ŏ��߂ĂP�X�W�O�N��㔼�e���r�L����V���L����𗽉킵������P�X�W�X�N�V�����D��A�P�X�X�W�N�ȍ~�Ăуe���r���D����ۂ�����B
�e�}�̕ʂɍ����܂ł̗�����T������Ƥ�V���L����V�F�A�͂P�X�T�V�N64.4%�ł��������P�X�T�O�N�㤂U�O�N�㤂V�O�N���ʂ��ĊT��50%���ێ����Ă�����P�X�W�O�N��㔼�ɓ���40%��ɒᗎ�������̂̂P�X�X�O�N��ɓ���Ă�50%��𒆐S�ɐ��ڂ��Ă���
�e���r�L����V�F�A�͂P�X�T�V�NHBC�e���r�J�ǎ���6.0%����X�^�[�g���N�X�m���ɃV�F�A���g�債40%���ێ����Ă������P�X�W�O�N��㔼�ꎞ��30%��܂Ō�ނ������̂̂P�X�W�T�N�ȍ~�ĂуV�G�A��߂�40%�㔼����P�X�X�X�N�ł�50%������V�F�A�ƂȂ����B����ɑ����W�I�L����V�G�A�͂P�X�T�V�N���_�ł͐V���Ɏ���29.6%�̃V�G�A�ł��������P�X�U�O�N�e���r�ɒǂ�������Ĉȍ~�N�X�V�G�A�������A�P�X�U�R�N�ɂ̓V���O����8.8%�ɗ��܂�����ȍ~�N�X�ᗎ�X�������������A�P�X�V�O�N6%�ɉ����̌��6%���ێ����¤�P�X�W�O�N��ɂ�7%��ɃV�F�A�A�c�v������������P�X�X�O�N��ɓ����Ă����5%�䂩��4%��ւƉ��~����H���Ă��茻�݃��W�I���f�B�A�͌��������ɔ�����Ă���
�@
6-7�ł͓d�ʐ��v�̓��{�̍L����𒆐S�ɂP�X�W�X�N�ȍ~�̖k�C���n��}�X�R�~4�}�̍L�������z�̐��ڂƤ�V������W�I��e���r3�}�̂̍L����V�F�A�������Ă�����P�X�W�T�N�ȍ~�k�C���n��ł������Ԃ̔O��ł������e���r�L����V���L�����ǂ��������[�f�C���O���f�C�A�Ƃ��Ẵ|�W�V�������蒆�ɔ[�߂�����P�X�W�X�N�ȍ~�Ăт��̒n�ʂ�V���ɏ����Ă����B�������Ȃ���o�u������㗼�҂̃V�G�A�͋͏��Ȃ�������̍����k�߂��ڂ��Ă����B�������N3�}�̂��P�O�O�Ƃ���V�F�A�͐V��51.8%�ɑ��e���r42.7%��9.1%�̊J�������������P�X�X�V�N�ɂ͂��̍���1.3%�Ək�܂����̂ł��顂����ĂP�X�X�W�N�Җ]�̃e���r�L����D���̎����}�����B���ケ�̗D����ێ����Ă������߂ɉ��Ƃ��Ă��D�y�𒆐S�Ƃ��铹���s��ł̃V�F�A�A�b�v����Ώ����ƂȂ�ł��낤��@���̂��Ƃ́A����܂ʼn��x���w�E�������ł���B���̍��ł̓e���r�e�Ђ̌��Z���Ɋ�Â������̐��ڂ������邪��k�C���n����P�X�W�X�N�P�O���P���e���r�k�C�����J�ǂ��܌n��̐����m������������T�ǂƂ������lj�������}���ăe���r�L���������n��Ԥ���ƎҊԂ̋����͂��̋ɂɒB���Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��
�@
�}�@55 �k�C���n��e���r�ljc�Ǝ�������
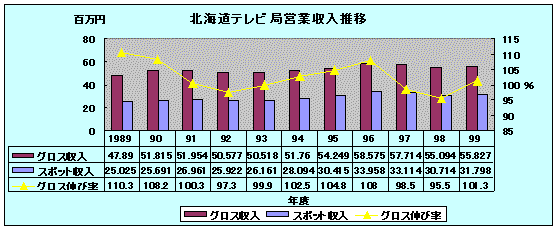 ��̃O���t�͖k�C���n��e���r�ǂ̎������ڂƁA�L�ї��̐��ڂ����������̂ł���B* TVh�̃X�|�b�g�����͂P�X�X�P�N�x���v�サ�Ă���B
�O���t�̎������ڂ͔�r���Č��Ă���������e���r���������{�A�k�C���̌o�ρA�i�C�̓����Ɩ��ڂɊ֘A���Đ��ڂ��Ă��鎖�������邾�낤�B
�@���A�X�|�b�g�����̃E�G�C�g�͔N���ɂ̓e���r�e�ǂ̎����̒��ő����̌X���ɂ��邱�Ƃ𗠕t���Ă���B�P�X�W�W�N�x������e���r�S�ǎ���̒n��X�|�b�g������23.413�S���~������ĂP�X�W�X�N
�V����TVh�������T�Ǒ̐��ƂȂ����B�T�ǂ̏W�v���n�܂����P�X�X�P�N�x�̒n��X�|�b�g������26.961(�S���~)�ł��������A�P�X�X�X�N�x�͂��̐�����31.798(�S���~)�ƂȂ肱�̊�4.837�S���~(117.9%)�̐L�т���������@
�@
������W�I�ɂ��Ă͂P�X�W�Q�N�k�C���n���O�Ԗڃ��W�I�ǂƂ��ăG�t�G���k�C�����J�ǂ�������k�C���n�惉�W�I�������P�X�W�W�N�x�O�Ǎ��v��6.966�S���~�ƂȂ菇���Ɏ�����L���ĂP�X�X�O�N����}�����
�}�@56�@�k�C���n�惉�W�I�ljc�Ǝ�������
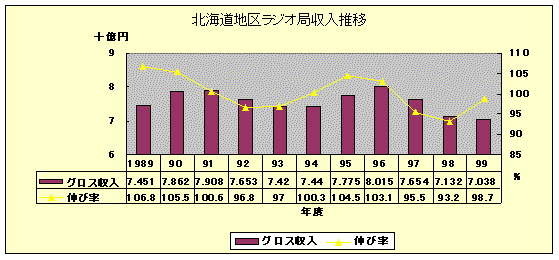 ��̃O���t�͖k�C���n�惉�W�I�e�Ђ̎����̐��ڂ����������̂ł���
�k�C���n��ł͂P�X�T�Q�N����HBC���W�I1�ǎ��㤂P�X�U�Q�N��STV���W�I�̊J�ǂɂ��2�ǎ���ƂȂ�A�����ĂP�X�W�Q�N�̃G�t�G���k�C���̊J�Ǥ�����P�X�X�R�N�Ƀm-�X�E�G�[�u���J�ǂ����n��I�ɂ͂P�X�T�Q�N��P�X�U�Q�N��P�X�W�Q�N��P�X�X�R�N�ƂP�O�N��Q�O�N���݂ŊJ�ǂ��꤂�����AM�Q�ǤFM�Q�ǂ̂S�Ǒ̐����m�������
�����Ŏ��_��ς���AM�FM���W�I�̎���������Δ䂵�Č���Ƥ���̃O���t�̗l��AM���W�I�Q�� �͔N�X�V�F�A�𗎂Ƃ��AFM���W�I�Q�ǂ��V�F�A�A�b�v�Ő��ڂ��Ă��鎖�������o���悤�
�@�}�@57�@�`�l�E�e�l���W�I�����V�F�A
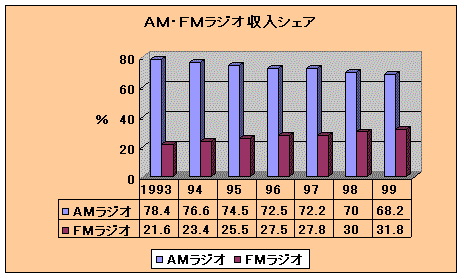 �@ �@���W�IAM�EFM�ǂ̎����g�����h�ɂ��Č����Ă������A�p�x��ς��Ă��̎����̒n��I�V�F�A�͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��͂��邱�Ƃ�����̃��W�I�̉c�Ɗ����̊������Ǝ����g����w�������ŋɂ߂ďd�v�ȃe�[�}�[
�@ �ł��낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�}�@58�@�k�C���n�惉�W�I�ǒn��ʎ����V�F�A
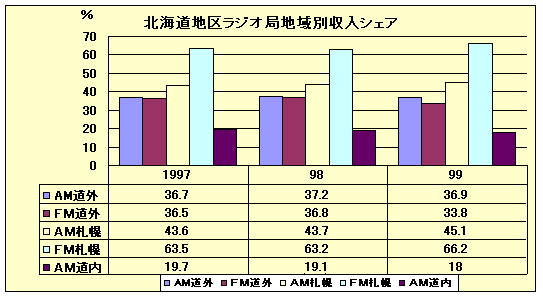 �@
��̃O���t���������ʂ�A���W�I�������ߔN�͎D�y���𒆐S�Ƃ��������V�G�A�����܂��Ă���A���̖ʂ�����D�y�̉c�ƑΉ������������E����傫�ȗv���ł��邱�Ƃ������ł��悤�B�Ƃ͌����D�y�������n���G���A�̎�����AM�ǂ̃P�[�X�ł�20%�߂��V�F�A��L���Ă���A�����AM���W�I�̂�����(���)�������n��̍L���\�[�X�̍X�Ȃ锭�@���d�v�ȃe�[�}�[�ł���B
�@
�o�ώY�ƏȂ��S���L���Ǝ��Ə���Ώۂɂ��Ď��{���Ă��颓���T�[�r�X�Y�Ǝ��Ԓ�����ͤ�d�ʓ��{�̍L����Ƃ͈�����p�x����L���Y�Ƃ̎��Ԃ�����ɂ��Ă��钲�������ł��顒��߂̎����i�Q�O�O�O�N�j���Q�l�ɕ����N��̖k�C���L���s���������
�Ώۂ͓����L���Ǝ��Ə��ł��邪�P�X�W�X�N�̎��Ə����X�T���P�X�X�X�N�ɂ͂P�R�S�ƂP�O�N�]���40%���̑��������Ă���B����L����͂���玖�Ə��̔N�Ԃ̔��㍂���W�v�������̂ł��邪������ł͍L����̓����z�Ƃ��Ď�舵������̍��ɋL�ڂ���O���t�͏�L�����̏W�v�Ɋ�Â������̂ł���B���̓��v�͒n�����Ə��̔���z����Ƃ��Ă���̂Ŏ��ۂ̔}�̎����Ƃ͈قȂ�A�T�O�I�ɂ͒n���L����Ɨ������ׂ����̂ł��낤�B
*�o�ώY�Ə� ����T�[�r�X�Y�Ǝ��Ԓ��� �L���ƕ҂�蔲��
�}�@59�@�k�C���n�惁�C���R�}�̍L������z����
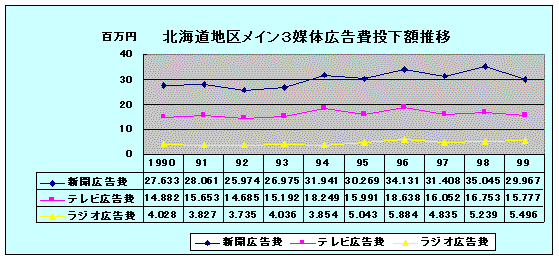 �}�@60�@�k�C���n�惁�C���R�}�̍L�������z�V�F�A���� �@
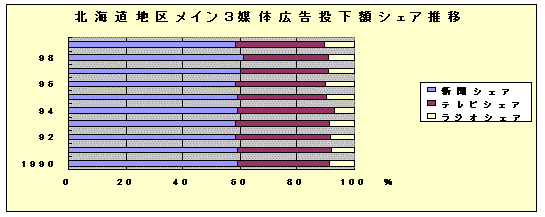 �}�@61�@�D�y�s�̔}�̕ʍL�������z���� 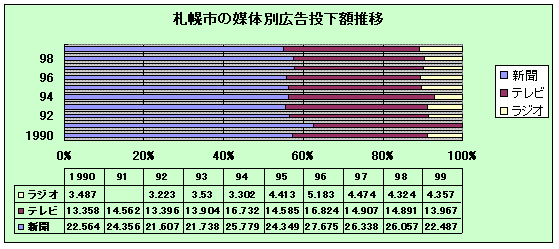 ��̃O���t�͖k�C���G���A���瓊�����ꂽ�L����ł��褑O�i�Ő������������l�ɓd�ʂ̍L����Ƃ̔�r�ł͓��O�L���肋����L����̓��̓����L����ɑ���������̂ł��顂��̒����ɂ���Ă��V���L����̖k�C���n���L�������ʂ�3�}�̒�60%���߂Ă��褒n���L����̖ʂł��D�ʐ���ێ����Ă��邱�Ƃ������ł��顎��ɎD�y�s�̍L���Ǝ��Ə��̔N�Ԕ��㍂�̐��ڂ����邱�ƂƂ���B���̃O���t�������悤�ɎD�y�s�̍L�������z�������N�x�ɓ���P�X�X�Q�E'�X�T�N�E'�X�W�E'�X�X�E'�O�O�N�ɂ́A�V���E�e���r�E���W�I�̎O�}�̂Ƃ��O�N���т��N���A�o�����������t���ɔ����ꂽ�B�@�@�@ �@
�����ŏ�ɍL���s��Ƃ��Ă��D�y�ƑΔ䂳��镟���ɂ��Ċ���̎�������Ɍ����Ă݂����B
�O���t�͓d�ʒ������������p �������A�P�X�X�V�N�k�C��VS�����̂S�}�̂̃V�F�A�� 44.6%vs55.4%�ł��������A�Q�O�O�O�N�ɂ͖k�C��42.4%�ɑ�������57.6%�Ɗi�����g�債�Ă���B �}�@62 �D�y�E�����L����V�F�A��r �@�@�@ ����Ɋ֘A���ĂP�X�X�W�N�Q���Q�W����[�T���_�C�������h]�ɓ��W�L���Ƃ��ĎD�y�sVS�����s�o�ϗ͔�r���ڂ����Ă��邪�A���̋L����~���E��ŏЉ�����B����ɂ��ΐl���͎D�y�s175���l�A���镟���s��123���l(96�N�Z����{�䒠)�őS�������L���O�S�ʂƂV�ʂɈʒu���Ă���B�������s�������Y(GDP)�̖ʂł͎D�y�s6��5151���~�A�����s6��1771���~�ł����l���Ŋ���ƎD�y�s��372���~�A�����s502���~�Ƒ����̊J��������B���A���Y�ʂ̎w�W�ł��鐻���i�o�z��������̍�������A���̓I�ɎD�y�s�͕����s�ɔ�ׂčH�Ɛ��Y�͂��Ⴍ�A�����Ƃ����Ȃ����ʂ�\���Ă���B(���̎��͐�ɎY�ƍ\���̍��ő�Y�Ƃ̏��Ȃ����Ƃ��L�q����)�B����ɑ��s�����x�o�ɂ��Ăł��邪�A�l������r����ƎD�y�s4��2063���~�A�����s2��8512���~�Ƒ傫�ȍ�������B���̎��͎D�y�s���̏�����̍�������Ă���B���̑��l�X�Ȕ�r���Ȃ���Ă��邪�A�s�ꐫ�E�o�ϗ͂ɂ��Ă͎���I����͂���ɂ���A�܂��܂��D�y�ɂƂ��Ă��D�ʂȖʂ����X������̂ƍl�����A�L���ʂŎD�y�s�̗D�ʐ����������ׂɂ�����̌o�ϖʂł̊������ɂ��L���s��̊g��ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||